ホーム
東京ドライビングサポートメディア
東京ドライビングサポート
メディア
お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。
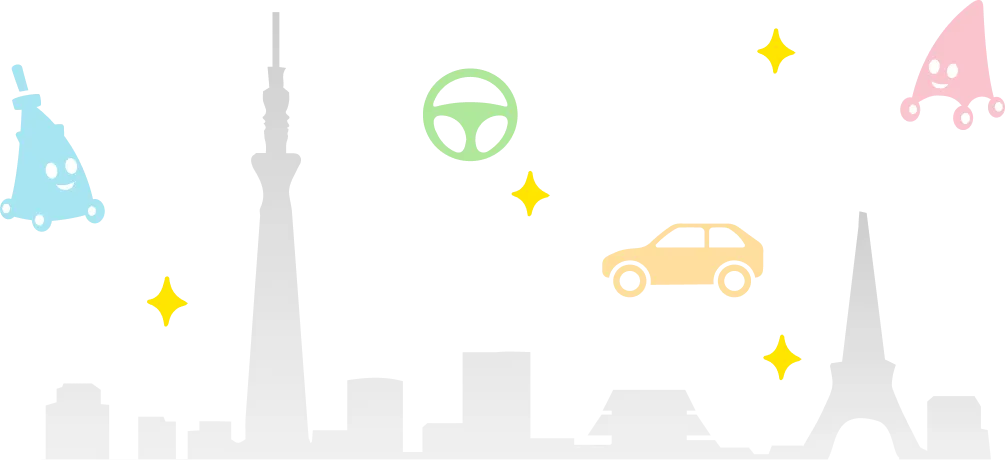
「えっ、自分が逆走していたなんて…?」 2025年7月、長野県飯田市で75歳の男性が交差点を逆走し、対向車と衝突する事故が発生しました。
男性は「標識が見えなかった」と語っており、NHK長野「高齢ドライバーの車 交差点で逆走し衝突 2人けが」として全国で報道されました。 また同時期、栃木県でも90代の男性が住宅街の一方通行を逆走し、複数車両に接触する物損事故が発生。
こちらもとちぎテレビ「住宅街で高齢者の車が逆走」としてニュースで取り上げられました。 こうした逆走事故は高齢ドライバーに限った話ではありません。 標識の見落とし・道の錯覚・ナビ誤案内による逆走は、ペーパードライバーや運転ブランクのある方にも十分起こりうるのです。 とくに東京都内では、Y字路・時間帯指定の一方通行・視認しづらい標識などが重なることで、自分でも気づかないうちに逆走していたというケースが後を絶ちません。 そして、これらの事故の根本には、単なる運転スキル不足ではなく、「見る → 認識 → 判断 → 操作」という“危険予測の4ステップ”が機能していないという課題があります。 その判断が必要な箇所が東京都内には多く存在します。そんな逆走事故は“誰にでも起こりうる”東京都内で起きやすいシーンと場所を読者のために注意喚起としてご紹介します。
【基礎的知識】逆走の多くは「標識の見落とし」──知らなかったでは済まされない事故の回避法とは?
都心部で起こる逆走事故。その多くが「標識を見ていなかった」「意味を誤解していた」という“認識不足”が原因です。
特にペーパードライバーや慣れない道を走る方は、「見たことはあるけど意味は知らない」標識が逆走に直結することも。
ここでは、逆走につながる主要な標識をあらためて整理し、「見る・読む・判断する」力を養いましょう。
逆走を防ぐために知っておくべき標識一覧とその正しい読み方
【1】進入禁止(赤丸に白線)|最も多い逆走原因の標識
進入禁止標識この標識は「車両の進入を禁止する」もので、逆走リスクの最も高いポイントに設置されています。
特に見落としがちなのは「時間制限付き」や「補助標識あり」のパターン。
夜間・早朝に「今は入っていいのでは?」と勘違いしやすいため、補助標識も必ずチェックしましょう。
【2】一方通行(青地に白矢印)|逆向きからの進入は“逆走”
一方通行標識この標識は「車両の通行方向を一方に限定」するもので、進入方向を間違えると即逆走になります。
「後ろから見たときに矢印が見えない」ため、反対側から進入しやすくなる盲点があります。
特に都心の住宅街では角度のある交差点で視認しづらく、GPSやナビを過信しないことが重要です。
【3】車両進入禁止(白地に赤円+車マーク)|原付・自転車は除外される場合も
車両進入標識この標識は「特定の車両は進入禁止」であることを示しますが、補助標識で例外がある場合が多いため注意が必要です。
「原付・自転車除く」「許可車両のみ可」などが小さく書かれており、読み飛ばすと逆走と見なされるリスクがあります。
逆走事故は“誰にでも起こりうる”|東京都内で起きやすいシーンと場所
【Y字路】中野区中央2丁目30-5|逆走が起こりやすい分岐交差点
■ なぜここが危険なのか? この場所はY字の交差点になっていて、左右どちらにも道が分かれています。
まっすぐ行けそうに見える道でも、実は「進入禁止」だったりするため、標識を見落とすと逆走につながることがあります。
夜間や初めて通る方は要注意。
実際、あまりにも逆走が多いため「車両進入禁止」看板が設置されているほどです。 ■ 危険を防ぐための考え方 【1. まずは見る(視覚のポイント)】 交差点手前では、「地面の白い矢印」と「左右にある一方通行標識」をセットで確認しましょう。
「なんとなく」で進まず、標識の示す通りに。 【2. どう考える?(情報の整理)】 「白い矢印=進んでよい方向」
「一方通行標識=入ってはいけない方向」
この2つを頭の中で整理して、「◯と×をつける」ような感覚で判断します。 【3. 万が一のために(もし判断が難しいとき)】 標識が見づらい、またはどちらに進めばいいか迷った場合は、いったん停止して確認するのが最も安全です。
「もし対向車が来たら?」と一度想像すると、逆走を防げます。 ■ 車の操作ステップ(逆走を防ぐ行動) 1. ゆっくり減速して後方ミラーを確認
2. 地面の矢印と標識をしっかり見る
3. 不安なときはその場で停止して確認
4. 正しい方向へウインカーを出して発進
5. 徐行で安全に進みましょう
一通標識と白線の「切れ方」で判断する進入可否|上級ドライバー向け危険予測トレーニング
一見見逃しがちな「停止線の形状」ですが、実は“進入してはいけない道”かどうかを判断する決定的なサインとなります。 上級者が危険を未然に回避するためには、次の3つの視点で道路を読む力が求められます。
【1】白線の状態を見る:停止線が「切れているか」「つながっているか」
- 白線がつながっている:この道路は一方通行の出口側である可能性が高く、正面から進入することは逆走になります。
- 白線が中央で切れている:進行方向である可能性があり、「進入可」と判断できるケースもあります。ただし、必ず「標識」と「周囲の交通状況」と照合してください。
【2】標識との照合:一通マーク・進入禁止・矢印標識との整合性
白線の形状だけでは確実な判断はできません。
必ず以下の標識とセットで確認してください。・赤丸の進入禁止:その方向からの通行は不可(=逆走)
・青矢印の一方通行標識:進行方向を明確に示すもの
・地面の進行矢印:地面に描かれた矢印が“補助的”に方向を示しています
【3】危険予測ステップ:白線+標識を見て「自分が入っていい道か」認知する
危険予測の精度を上げるために、以下の流れを習慣化することが重要です。 ① 視覚認知:交差点に近づく際に、標識・地面・白線に注目する ② 判断処理:「白線が切れている/つながっている」「標識はどうか」を瞬時に判別する ③ 予測行動:「この道に入っていいか/ダメか」「他車の動きと逆でないか」を考える ④ 操作判断:誤進入の可能性があれば即座に停止し、安全確認を再優先する
【4】さらに実践:一通の入口か出口かを瞬時に見極めるトレーニング
都市部では、白線の有無だけでなく「路面電車」「自転車レーン」「中央分離帯」など他要素も絡みます。 そのため、ペーパードライバーや再開者は、都内の実例(中野・板橋・新宿など)を用いた現地トレーニングが有効です。 東京ドライビングサポートでは、このような危険予測の上級編も踏まえたオーダーメイド講習を実施しています。
小竿インストラクターからのアドバイス:この「白線の切れ方」や「一通標識」との組み合わせによる判断は、運転を長くしてきた人でも見落としがちなポイントです。 特にY字路のように分岐が自然に広がっていく場所では、進入禁止の標識や白線のパターンに加えて、地面の矢印や周囲の車両の動きも総合的に見る必要があります。 例えば「白線がつながっているから通っちゃいけないかな?」「でも一通の標識が見えない…」といったケースでは、一瞬の判断ミスが逆走につながる可能性があります。 だからこそ、こうした「複数要素を見て判断する」トレーニングは、感覚ではなく頭で整理する型(フレーム)を持つことが重要です。
私の講習では、こうした危険予測の場面で
「どこに注目すればいいのか」「どう順序立てて考えるか」
といった“判断の順番”を具体的にお伝えしています。 「ただ走れる」ではなく、「状況を読める」ことが安全運転の鍵です。
🚗 都内は“判断ミス”が命取り。だからこそ、今こそ危険予測トレーニングを。 Y字路・一方通行・複雑な標識──
運転を再開したばかりの方にとって、東京都内の道は迷いやすく・間違えやすい落とし穴が多くあります。 当講習では、実際に逆走や接触事故が多発しているスポットを走行しながら、「どこを見て・どう判断するか」を段階的に学べます。 「標識が見えなかった…」と後悔する前に、今できる“危険予測スキルの可視化”を体験してみませんか?
【逆走注意】東京都新宿区百人町1丁目17-3付近|視覚トラップに注意すべき交差点
■ この交差点で事故・逆走が多発する理由: ・車道の幅が狭く、センターラインが見えにくい構造
・一方通行の「→」標識と「車両進入禁止」標識が同時に表示されており、視点によっては見落としやすい
・直前まで両方向通行だった道路が急に“一通”になるため、進行方向の変更に気づけない構造的トラップ
■ 標識チェック視点: 分岐手前で「車両進入禁止(赤丸に白帯)」と「一方通行(青矢印)」を確認しましょう。
地面には進行方向の矢印が薄く描かれており、“前方の進入禁止”に対して「自分はどこへ行けるのか?」の判断が必要です。
■ 危険予測のやさしい3ステップ: 【1. 見えるものを整理する】
「前方に赤い標識=入れない?」「青矢印の方向だけ進めるのか?」【2. 組み合わせて意味を考える】
「正面は進入禁止 → つまり自分は右か左に曲がるべき」【3. 自分の立ち位置とルールを照合】
「今いる道が二車線に見えても、一方は進入禁止の対向車線かもしれない」
■ 車の操作ステップ: ・ブレーキを軽く踏みながら、標識と地面の表示を同時に確認
・右折/左折のどちらが許可されているか、矢印を目視で判断
・対向車が来る“ように見える道”は実は一方通行かを慎重に確認し、安全に進行しましょう
小竿インストラクターからのアドバイス:
「ここの場所では、“白線が切れている=進入OK”と短絡的に考えないことが大事です。まず注目すべきは、白線の切れ方が意図的かどうか。物理的に塗装が途切れていても、標識や矢印が“進入禁止”を示していれば、当然通行はNGです。
また、白線だけでなく地面の進行方向矢印、左右の標識の位置、周囲の車の流れなどを複合的に見てください。特に一方通行の標識は、設置角度によっては“運転席からは見えない”ことがよくあります。だからこそ、標識が見えなかった=進入可能という判断は非常に危険。見えないことを前提に、“逆にここは標識があってもおかしくない構造だな”と予測を立てて行動するのが“上級者の運転”です。そして、たとえ自分が『行けそう』と思っても、対向車の有無やブレーキ痕、交差点の死角の有無から、“この道は対向車が来る設計か?”という想像を働かせましょう。
危険予測は“視覚情報”よりも、“構造理解”と“場の空気を読む力”が試されます。」
🚗 都内は“判断ミス”が命取り。だからこそ、今こそ危険予測トレーニングを。 Y字路・一方通行・複雑な標識──
運転を再開したばかりの方にとって、東京都内の道は迷いやすく・間違えやすい落とし穴が多くあります。 当講習では、実際に逆走や接触事故が多発しているスポットを走行しながら、「どこを見て・どう判断するか」を段階的に学べます。 「標識が見えなかった…」と後悔する前に、今できる“危険予測スキルの可視化”を体験してみませんか?
【交差点注意】東京都渋谷区南平台町12-10付近|南平台交差点の見落としやすい標識と逆走リスク
■ 1. まずは見る(視覚のポイント) 南平台町交差点付近は、住宅地と幹線道路が交わる構造上、進入禁止の標識が目線より高い位置に設置されており、すれ違いに集中すると見落としやすいです。
歩道や電柱、植栽などの視覚ノイズが多く、標識確認のタイミングが限られます。まずは「標識を探す」つもりで走行を。 ■ 2. どう考える?(情報の整理) ・周囲のクルマの動きに違和感がないか(自分と逆方向に車が進んでいないか)
・進もうとしている道に一方通行の矢印はあるか?
・都心のナビはズレる場合が多く、「ナビより標識」を優先する判断が必要です。 ■ 3. 万が一のために(もし判断が難しいとき) ・ハザードを点けて減速、交差点手前で一時停止
・標識を再確認し、無理に進入しない
・後方車に迷惑をかける前に一度スルーして回避する冷静さが重要です ■ 車の操作ステップ(逆走を防ぐ行動) 1. 渋谷・南平台エリアは見通しが悪く歩行者も多いため、10km/h以下の徐行が基本
2. 標識と車線(実線・破線)を必ず目視で照合
3. ナビが「右折」と示していても標識が進入禁止なら絶対に従わないこと 4. 一度の判断ミスで逆走に繋がりやすいため、交差点での減速+左右確認を徹底しましょう。
小竿インストラクターからのアドバイス: 「“標識の位置が高い”“補助標識が読みづらい”と感じた時点で、進入そのものを一旦保留する勇気が重要です。 とくに渋谷区南平台町のような住宅密集地では、クルマ同士がすれ違えない狭路が多く、一度進入すると後戻りが難しいケースもあります。 ■ 私が教習でお伝えしているアドバイスは──
・“標識が複雑”と感じた瞬間に、必ず一時停止
・目視で「原付・自転車除く」と読めなければ、原則として進入しない
・周囲に交番や郵便局などがあれば、建物の位置関係から一方通行の流れを推測 また、「前方に進む車が軽自動車や原付だった場合」は、“自分と同じ車種かどうか”を確認し、安易についていかないこと。
たとえナビが案内していても、標識が“最上位ルール”です。 都市部では“見落とさない目”よりも、“立ち止まれる心”が安全に直結しますよ。
【逆走リスク高】東京都豊島区東池袋4丁目27−10付近|池袋六ツ又交差点の複雑な分岐・高所標識・進入禁止の罠
■ 1. まずは見る(視覚のポイント) 池袋六ツ又交差点は、6方向に道路が分岐し、視覚情報が錯綜しやすいエリアです。
特に標識が高所または分岐中央の支柱にあり、目線から外れやすいため、早めに減速して“標識を探す意識”が重要です。
また、左右を小刻みに見て、道路中央に進入禁止の標識があるかを確実にチェックしてください。 ■ 2. どう考える?(情報の整理) 分岐地点での判断は、迷いが出た時点でリスクです。
・自車が向かおうとしている道路に「白い矢印」や「一方通行標識」があるか ・対向車の動き(歩行者・自転車の向き)に違和感がないか
・ナビに頼りすぎず、現地標識での判断を優先することが鉄則です。 ■ 3. 万が一のために(もし判断が難しいとき) ・一時停止してハザードを点ける
・落ち着いて左右確認し、標識を再確認
・後続車がいる場合は、ウインカーで停車の意志を明確に
進入が不安な場合は一度直進して、安全な場所でUターンする判断も大切です。 ■ 車の操作ステップ(逆走を防ぐ行動) 1. 手前で十分に減速(5〜10km/h以下が理想)
2. 分岐に差しかかる前にウインカーを出すことで周囲に意思表示 3. 標識と車線の白線を照合し、必ず「自分の車が入ってよいレーンか」を確認
4. 少しでも不安があればアクセルを踏まない・一時停止 5. 誤って逆走方向に進みかけたらすぐに停止・後退せずに周囲確認→進入回避を徹底
小竿インストラクターからのアドバイス: 池袋六ツ又交差点のように、道路が複数方向へ分岐する場所では、「標識の高さ」「位置」「背景との重なり」によって視認性が極端に下がることがあります。 特にこの交差点では、標識が高所や中央島の支柱に取り付けられているため、運転中の視線では見落としがちです。
“進入禁止”や“一方通行”の標識を見落とすと、誤進入からの逆走につながる可能性が高いため、私は必ず以下のような行動を推奨しています。 ■ 迷ったら一時停止、そして「見に行く勇気」
交差点進入前に「どこが進入禁止なのか」「自分の車はどこへ行けるのか」を、フロントガラス越しではなく一歩下がった視点で考えることが重要です。
迷いが出たら、とりあえず“止まる”──これが、事故の連鎖を断ち切る初動になります。 ■ 見落としやすい状況こそ「停車+確認」で防ぐ
・信号が青でも、標識が不明なら進入を控える
・「他の車が進んでいるから大丈夫」は危険な思い込み
・仮に、原付や軽自動車が進んでいたとしても、それは「その車両が進める条件を満たしているから」に過ぎません。
自分の車種・大きさ・進入方向に合致しているかを冷静に判断することが必要です。 ■ 判断に自信が持てない時は、“一旦スルー”も正解
安全な道路でUターンする、ナビの再検索を待つ、近くの交番で確認するなど、「進まない勇気」は、安全な運転者に共通する判断力です。 池袋六ツ又のように情報が錯綜するエリアでは、「ナビより標識」「標識より判断の余裕」が大切です。
分岐点では常に、“自分の進路に入ってはいけない要素があるか?”を探す意識を持ちましょう。 ── 見る・考える・止まる。それだけで逆走は防げますよ。
🚗 都内は“判断ミス”が命取り。だからこそ、今こそ危険予測トレーニングを。 Y字路・一方通行・複雑な標識──
運転を再開したばかりの方にとって、東京都内の道は迷いやすく・間違えやすい落とし穴が多くあります。 当講習では、実際に逆走や接触事故が多発しているスポットを走行しながら、「どこを見て・どう判断するか」を段階的に学べます。 「標識が見えなかった…」と後悔する前に、今できる“危険予測スキルの可視化”を体験してみませんか?
千代田区神田駿河台1丁目1付近|【逆走注意】本郷通りとの分岐で誤進入しやすい立体交差
■ なぜここが危険なのか? 神田駿河台の交差点は、明大通りから本郷通りに分岐する立体交差です。
一見すると広く見通しの良い道ですが、進入禁止の標識や白線のレーン区切りが非常に見落としやすい構造となっています。
特に左車線にいながら誤って中央レーンへ合流してしまうと、進入禁止の道に逆走するリスクが高まります。
■ 危険を防ぐための考え方 【1. まずは見る(視覚のポイント)】 標識は分岐手前の高所または支柱の中央に配置されており、見落としやすい構造です。 手前から減速し、標識を“探す意識”を持って走行しましょう。特に夜間・雨天では見えづらくなるため、早めの準備が重要です。 【2. どう考える?(情報の整理)】 「ナビの指示よりも標識優先」──この意識が最も大切です。
・進もうとする方向に一方通行標識や進入禁止マークがないか?
・周囲の車・歩行者の進行方向に違和感がないか?
・車線の白線が明確に「進入可」となっているか?
これらを瞬時に判断する冷静さが求められます。 【3. 万が一のために(もし判断が難しいとき)】 「わからない=止まる」
この判断が命を守ります。
・交差点手前で一時停止+ハザード点灯
・左右の標識・標示を再確認
・後続車が来ていたらウインカーで“停車の意志”を伝える
それでも不安な場合はそのまま直進し、次の安全な場所でUターンしましょう。 ■ 車の操作ステップ(逆走を防ぐ行動)
1. 手前で減速(理想は10km/h以下)
2. 分岐直前でウインカーを出して意志表示
3. 標識と白線の一致を確認し、正しいレーンか判断
4. 少しでも迷いがあれば一時停止・後退はしない
5. 誤進入しかけたらその場で停止し、周囲確認を徹底
小竿インストラクターからのアドバイス:
神田駿河台の分岐ポイントは、見た目が広く開けていて安心感がある反面、標識や進入禁止の情報を“見落としやすい構造”になっています。特に初めて通る方は「ナビが指示したから」「前の車が曲がったから」と思考停止してしまいがちですが、道路の標識や白線こそが“絶対のルール”です。ナビよりも現場の標識を優先する意識を、常に持ってください。また、こうした分岐点では、後続車や周囲の流れに焦って判断してしまう方もいますが、「わからなければ止まる」という選択肢が命を守ります。講習中でもこの地点は練習に含めることが多く、「視線の置き方」「標識の探し方」「進路選択の迷いへの対処」などを丁寧にサポートしています。一見シンプルな道ほど“思い込みの落とし穴”がある──それが都市部の分岐交差点の怖さです。
危険予測の基本をふり返る|“見えていたのに見えていなかった”落とし穴
ここまでご紹介した通り、東京都内では「標識の見落とし」や「車線の思い込み」「ナビに従って逆走」といった事例が数多く報告されています。 特に一方通行や進入禁止の標識は、視界の“上部”や“柱の中間”に設置されていることが多く、慣れないエリアではドライバーが気づけないまま通過してしまうことも。
「見ているつもりでも見えていない」──これが、都市部に潜む最大の危険です。 逆走や誤進入の多くは、数秒前の「判断の迷い」や「認知のズレ」から始まっています。
つまり、“いかに先に気づけるか”が、事故を未然に防ぐ鍵となるのです。
東京ドライビングサポートでは、これまで多くの受講者が「危険予測の甘さ」に気づく瞬間をサポートしてきました。 「判断が遅れたらどうなるか」「標識を見落とすとどんな状況に陥るのか」──現実に即した講習の中で、体感的に理解できる場面を積み重ねています。 そのうえで私たちは、こう問いかけます。 「あなたは、本当に“予測”できていますか?」
あなたは本当に“危険予測”できていたか?|逆走・誤進入の裏にある心理と見落とし
ここまでの章では、東京都内のリアルな危険事例をもとに、「逆走」「標識の見落とし」「交差点分岐ミス」といった具体的なケースをご紹介しました。 読者の皆さまはどう感じたでしょうか?
「自分なら気づけた」「こんな道、走ったことがある」「いや、これは気づけなかったかも…」 実はこうした“認知と判断のズレ”こそが、事故の入り口です。
そしてそのズレは、多くの場合、「知っていたのに」「見えていたのに」という“思い込み”から生まれています。 見落とされやすい標識には、共通点があります。 ・視線の死角(高い位置、柱の中間)
・道路上の白線が目立ちすぎて標識がかすむ
・ナビの音声が先入観を強めてしまうつまり、注意している“つもり”では防げないのです。 「わかっていたはずなのに、間違えた」という体験こそが、まさに危険予測の盲点です。 東京ドライビングサポートでは、運転スキル以前に“危険を予測する習慣”こそが安全運転の土台であると考えています。 「気づける力」を養わなければ、運転はいつか“勘”に頼るものになってしまう。 それは、家族を乗せるあなたにとって、あまりに危うい運転の形です。 「一度も事故を起こしていない=危険予測ができている」とは限りません。
事故が起きていないのは、単に“運”かもしれない。 その運任せの状態を抜け出すには、予測の技術を学ぶしかありません。 次章では、あなたが実際の運転中に“何を見て”“どう判断し”“どんな行動をとるべきか”を明確にするための「危険予測トレーニング編」をご紹介します。 「なぜあの人はミスをしたのか」ではなく、「自分ならどうしたか?」という視点を持って、次に進んでください。 「予測力」は、訓練によって誰でも身につけられる力です。
「予測力」は誰でも伸ばせる──東京ドライビングサポートが教える危険予測トレーニングとは?
「危険予測」は、特別な勘や経験だけで身につくものではありません。
むしろ大切なのは、「見方」と「考え方」を知っているかどうか。 東京ドライビングサポートでは、ペーパードライバー講習の中で、以下の3つの力を重点的に鍛える危険予測トレーニングを提供しています。 ① 見る力:「どこに危険が潜んでいるか」を視野で捉える ・交差点・駐車場・横断歩道など、危険が集中する“予測スポット”の認識
・目線の動かし方、ミラー確認のタイミング、歩行者や自転車の動きの予測
・「見落としやすい場所」に対する習慣的なスキャン技術の訓練 ② 考える力:「何が起きるか」を想像する予測思考 ・「この状況で子どもが飛び出したら?」「対向車が右折してきたら?」
・“かもしれない運転”ではなく“起きうる行動を具体的に描く”想像訓練
・インストラクターとの対話を通じて、1秒先の判断を習慣化する思考トレーニング ③ 行動する力:「予測した上でどう運転するか」の実地練習 ・加速・減速・車線変更など、予測にもとづく操作判断の実践
・「何かあるかもしれない」と思った地点で、自然に減速できる運転設計
・予測を運転技術に転換できる“実地での再現性”を高める こうしたトレーニングを通じて、“たまたま事故が起きていない状態”から“事故を回避できる運転”へと進化することが目的です。 「なぜあの人はミスをしたのか」ではなく、「自分ならどう判断し、どう動くか」 ──この視点を持ち続けることが、安全運転の第一歩になります。 予測力は才能ではありません。 見方と考え方を正しく身につけ、場数を踏めば、誰でも安全な運転者になれる。
東京ドライビングサポートの危険予測トレーニングは、そのための最短ルートです。
🚗 都内は“判断ミス”が命取り。だからこそ、今こそ危険予測トレーニングを。 Y字路・一方通行・複雑な標識──
運転を再開したばかりの方にとって、東京都内の道は迷いやすく・間違えやすい落とし穴が多くあります。 当講習では、実際に逆走や接触事故が多発しているスポットを走行しながら、「どこを見て・どう判断するか」を段階的に学べます。 「標識が見えなかった…」と後悔する前に、今できる“危険予測スキルの可視化”を体験してみませんか?
【安全運転は“気づき”から始まる】ペーパードライバーの再スタートに必要な「危険予測力」
最後に|危険を「避けられる人」になるために
誰しも、運転中にヒヤリとした経験はあるはずです。
しかし、その瞬間を「学び」に変えられるかどうかが、安全運転を続けるための分かれ道になります。運転に対して不安を感じるのは、決してマイナスではありません。
むしろ、それは「見えていない危険に気づこうとする力」がすでに芽生えている証拠であり、安全運転の入り口に立っているということです。重要なのは、目の前にある“運転操作の技術”だけを見つめるのではなく、その裏側にある「想像力」や「観察力」に気づけるかどうか。
加害者にも被害者にもならないためには、単に車を動かせるだけでは足りません。
「もしこの先に子どもがいたら?」「あの車が急に曲がってきたら?」──そうした仮説を瞬時に思い描き、自然に減速できる人こそが、“危険を避けられる人”なのです。この力は、経験や勘ではなく、正しい見方と考え方を知ることで誰でも養うことができます。
そして、繰り返し練習を重ねることで、意識しなくても危険を察知できる「習慣」へと変わっていきます。私たち東京ドライビングサポートが提供するのは、単なる運転練習ではありません。
「見えない危険を、見えるようにする」「危険な場面で、迷わず行動できるようにする」。
この2つを徹底的に磨くことが、私たちの危険予測トレーニングの核です。運転は、一生続く生活の一部です。
だからこそ、誰かの命を預かるかもしれないそのハンドルを、「なんとなく」ではなく「確信を持って」握れるようになることが、最も大切なのです。予測力は、才能ではありません。 見方を学び、考え方を鍛え、少しずつでも実践を積めば、どんな人でも“危険を避けられる人”になれる。
私たちは、そんな「変われる力」を信じ、受講者一人ひとりに寄り添いながら、日々サポートを続けています。
出張型ペーパードライバー講習を手がける「東京ドライビングサポート」
記事監修:小竿 建(こさお けん)
教習指導員資格者証(普通) / 教習指導員資格者証(普自二)
運転適性検査・指導者資格者証 保有
長年にわたり自動車教習所の教習指導員として、多くのドライバーの育成に携わる。
警察庁方式運転適性検査の指導者として、運転者の特性に応じた安全運転指導にも従事。
令和元年には、長年の交通法規遵守と安全運転励行、交通事故防止への貢献が認められ、
練馬警察署長および練馬交通安全協会会長より感謝状を贈呈。
豊富な指導経験と高い安全運転意識に基づき、この記事の内容を監修しています。
本記事の企画・取材・構成について
本記事は、東京ドライビングサポートの広報・マーケティングチームによる現場取材と分析をもとに構成されています。
取材・企画・構成を担当したのは、広報ディレクター 板倉 智(いたくら さとし)。
これまで数多くの受講者にインタビューを重ねてきた板倉は、SNS運用やSEO対策にも精通し、
「伝わる・検索される・信頼される」広報・情報発信を推進しています。
【店舗名(Name)】 東京ドライビングサポート|出張ペーパードライバー講習・高齢者講習サポート
【住所(Address)】 〒175-0092 東京都板橋区赤塚4丁目18-8
【電話番号(Phone)】 0120-763-818
【営業時間】 毎日 9:00〜20:00(年中無休)
※講習スタートは9時〜/最終講習は19時台まで対応可能です。
【対応エリア】 板橋区・練馬区・北区・和光市・朝霞市などを中心に出張対応
【メールでのお問い合わせ】 info@tokyo-driving-support.jp
【講習予約はこちら】 ▶ 初回90分お試しコースを予約する(TimeRex)


