ホーム
東京ドライビングサポートメディア
東京ドライビングサポート
メディア
お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。
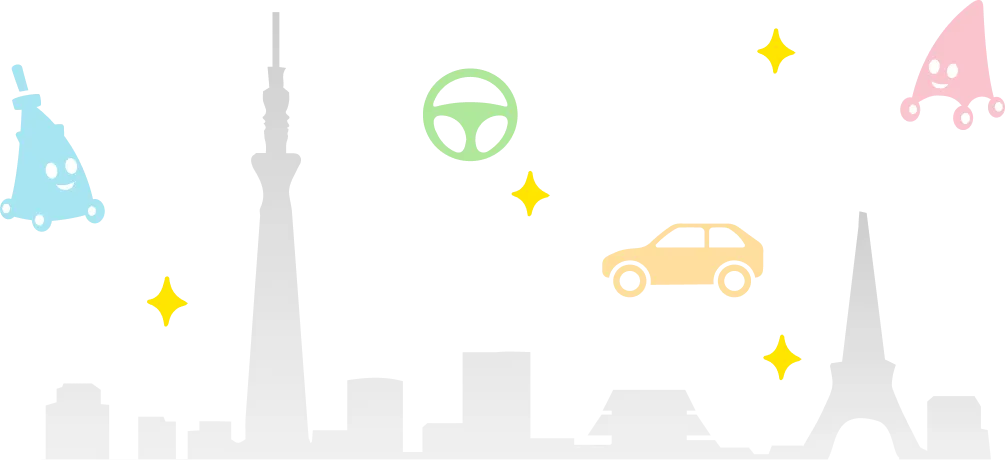
 【住宅街の危険予測講習】 見通しの悪い交差点では、標識や車だけでなく“歩行者や自転車の気配”にも注意が必要です。
【住宅街の危険予測講習】 見通しの悪い交差点では、標識や車だけでなく“歩行者や自転車の気配”にも注意が必要です。近年、交通事故件数は減少傾向にありますが、「ヒヤッとした」「事故寸前だった」という声は依然として多く聞かれます。
特にブランクのあるペーパードライバーにとっては、「見えているのに見えていない危険」に対応する力──すなわち危険予測力が極めて重要です。
一方で、クルマ自体の安全性能も進化を続けており、自動ブレーキや車線逸脱警報などのASV(先進安全自動車)技術が次々と実用化されています。
とはいえ、どの機能が自分にとって本当に必要なのか、迷う方も多いのではないでしょうか。
そんなときに参考になるのが自動車アセスメント(JNCAP)です。
これは独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)が国土交通省の指定を受けて行っている安全性能の評価制度です。
評価は以下の3つの観点から実施され、点数やランキング形式で公表されています。  【住宅街の危険予測トレーニング】 死角の多い交差点では、“出てこない前提”ではなく“飛び出してくるかもしれない”前提で走行する姿勢が大切です。
【住宅街の危険予測トレーニング】 死角の多い交差点では、“出てこない前提”ではなく“飛び出してくるかもしれない”前提で走行する姿勢が大切です。  【今この瞬間の判断が数秒後を変える】 交差点の安全は、信号や標識だけでなく“見えないリスク”を先読みできるかで決まります。
【今この瞬間の判断が数秒後を変える】 交差点の安全は、信号や標識だけでなく“見えないリスク”を先読みできるかで決まります。
- ① 衝突安全性能:正面・側面・後方など、衝突時の乗員保護性能
- ② 予防安全性能:自動ブレーキ、車線逸脱防止など、事故の未然防止に関わる装備
- ③ 被害軽減ブレーキ・歩行者保護性能:歩行者や高齢者に配慮した安全機能
JNCAPを活用すれば、「安全性が見える化」されており、価格やデザインだけに左右されず、命を守るクルマ選びが可能になります。
しかし、どんなに優れた装備を持つ車であっても、最終的に事故を防ぐのは運転する人の判断力です。
そこで今、注目されているのが「危険予測力を育てる講習」です。
東京ドライビングサポートでは、ただの運転練習ではなく、「この先にどんな危険があるか」を先読みしながら走るトレーニングを提供しています。
交差点や横断歩道、見通しの悪いカーブなどで「どんな動きが起きそうか?」を予測し、即時判断する力を養います。
この実践的なトレーニングは、教習所ではなかなか教わらない分野であり、以下のような方にとくにおすすめです
- ・ブレーキや右左折のタイミングに不安がある
- ・住宅街や狭い道での運転が怖い
- ・高齢の親や小さな子どもを乗せて安全に走りたい
- ・とっさの判断に自信がない
ASV技術+自分自身の“気づく力”。
この両輪がそろってはじめて、安心・安全なカーライフが手に入ります。
※本記事は政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5741.html)の情報を参考に構成しています。
導入:なぜ「危険予測」は、ペーパードライバーにこそ必要なのか?
 【住宅街の危険予測トレーニング】 死角の多い交差点では、“出てこない前提”ではなく“飛び出してくるかもしれない”前提で走行する姿勢が大切です。
【住宅街の危険予測トレーニング】 死角の多い交差点では、“出てこない前提”ではなく“飛び出してくるかもしれない”前提で走行する姿勢が大切です。 交通事故は「見えていなかったから」起こるわけではありません。
実際には、「見えていたけれど、次に何が起きるかを予測できていなかった」──この“認知のズレ”が原因であることが多いのです。
警察庁の統計でも、事故原因の上位に挙がるのは「安全不確認」や「予測運転の不足」。 つまり、“注意していたつもり”でも、状況の変化を読み取れていなければ事故に至るのです。
この「危険予測力」は、免許取得時にほんの一部しか教えられず、教習所のカリキュラムでも深くは扱われません。
特にブランクのあるペーパードライバーにとっては、運転操作以前に、「周囲を見る視点」や「変化を先読みする感覚」が大きく鈍っているケースが非常に多く見受けられます。
たとえば── ・交差点での“右折車と歩行者の同時確認” ・住宅街での“見通しの悪い交差点”での徐行タイミング ・路駐車両の陰から出てくる自転車や子どもへの注意
これらは、どれも“まだ見えていない危険”を先回りして想像することで、ようやく安全な判断が可能になります。
しかし、この予測力は教科書だけでは身につきません。必要なのは、実際の環境で「何を想像すべきか」を体で覚えていくプロセスです。
特に都市部や住宅街では「運転技術」よりも「予測力」こそが、最も重要な安全技術といえるでしょう。
東京ドライビングサポートでは、この“予測する力”を磨くために、実際の生活道路を走りながら「想像し、判断し、行動する」トレーニングを提供しています。 「見えなかった」ではなく「気づけなかった」をなくす──。その第一歩が、「危険予測力」を身につけることなのです。
危険予測とは何か?──知っておくべき「見る」と「想像する」の違い
 【今この瞬間の判断が数秒後を変える】 交差点の安全は、信号や標識だけでなく“見えないリスク”を先読みできるかで決まります。
【今この瞬間の判断が数秒後を変える】 交差点の安全は、信号や標識だけでなく“見えないリスク”を先読みできるかで決まります。危険予測とは、「今この瞬間の状況から、数秒後に何が起きるかを想像する力」です。
たとえば、交差点に近づくとき──前方に自転車がふらついているのを見たとします。
そのとき「もしかするとこの自転車、横断してくるかもしれない」と考えて減速できるかどうか。
この“想像して行動を変える”力こそが、まさに危険予測力です。
認知心理学の分野では「ハザード知覚(hazard perception)」とも呼ばれており、反射神経ではなく想像力・注意力・経験の積み重ねによって磨かれるとされています。
つまり、ただ目に映っているものを見るだけでは不十分で、その先の展開を「自分の頭でシミュレーションすること」が事故を未然に防ぐ鍵なのです。
この力が不足していると、減速すべきタイミングでそのまま走り続けてしまい、「ヒヤリとする瞬間」や「間一髪の回避」ばかりが増えていきます。
これは偶然ではなく、危険が“見えていなかった”のではなく、“予測できていなかった”ことが原因です。
こうした予測力の欠如は、ペーパードライバーにとって最も見えにくく、かつ重大なリスクになり得ます。
特に運転ブランクが長い方や、教習所以来ハンドルを握っていない方は、「危険予測をしているつもり」で運転していることが多く、実際には“想定が足りていない”というギャップに気づけていません。
ですが、この力はトレーニング次第で必ず取り戻すことができます。大切なのは「感覚を思い出すこと」ではなく、新しい視点で周囲を読む力を育てることです。
東京ドライビングサポートでは、「見えない危険」を可視化し、的確に予測する力を育てるために、実際の生活道路・交差点・住宅街・学校周辺などを舞台にしたリアルな講習を実施しています。
特徴的なのは、ただ運転させるのではなく、講師が同乗しながら「この先、何が起こりうると思いますか?」「今、誰に注意を向けていますか?」と問いかけ、その場その場で“予測の視点”を引き出す対話型トレーニングであること。
さらに受講者自身が考えながら声に出して運転する「実況中継方式」も取り入れています。自分の思考プロセスを言語化しながら走ることで、見落としていたリスクや判断の癖にも自然と気づくことができます。
こうした講習は、紙のテストや運転シミュレーターでは決して得られない、“実感をともなった予測力”の習得につながります。
特にブランクのあるペーパードライバーにとって、「なんとなく怖い」「何が怖いか分からない」状態から抜け出すきっかけになったという声も多数届いています。  【危険予測トレーニング】 住宅街では“出てくるかもしれない”という意識が事故を防ぎます。人と自転車の不意の横断に備える判断力が求められる場面です。
【危険予測トレーニング】 住宅街では“出てくるかもしれない”という意識が事故を防ぎます。人と自転車の不意の横断に備える判断力が求められる場面です。
教科書では学べないけれど、命を守るためには最も大切な力。 それが、私たちが講習で最も大事にしている「危険予測力」なのです。
🚗 危険予測に不安がある方へ──まずは無料相談から始めてみませんか?
運転中「どこを見ればいいかわからない」「とっさの判断が怖い」と感じている方に向けて、
東京ドライビングサポートでは、“危険予測”に特化した個別相談会を実施中です。
日常の運転シーンで不安に感じる場面をもとに、講師が丁寧にヒアリング・アドバイスいたします。
📘 実際の道で“予測する力”を鍛える90分間トレーニング
住宅街・生活道路・交差点など、事故が起こりやすい場所を走行しながら、
講師と一緒に「予測 → 判断 → 行動」を繰り返すトレーニングを行います。
実況中継形式や声かけ形式を取り入れ、机上では身につかない“実践力”をその場で体験できます。
【東京ドライビングサポートの実践講習】都市型エリアで磨く「危険予測力」──交差点・歩行者・停車車両への対応力を高めるトレーニング
 【危険予測トレーニング】 住宅街では“出てくるかもしれない”という意識が事故を防ぎます。人と自転車の不意の横断に備える判断力が求められる場面です。
【危険予測トレーニング】 住宅街では“出てくるかもしれない”という意識が事故を防ぎます。人と自転車の不意の横断に備える判断力が求められる場面です。都市部の中心街は、交通量と歩行者数が極めて多く、運転中の情報処理量が急激に増加するエリアです。
ペーパードライバーや運転ブランクがある方にとっては、視野の広さ・判断の速さ・心の余裕、すべてが試される“緊張感の高い場所”といえるでしょう。
東京ドライビングサポートでは、この都市型エリアでの危険予測をテーマに、実際の信号密集交差点や商業エリアを使った出張トレーニングを実施しています。
以下は特に頻出するリスクと、それに対する予測の視点・対策です。
🔸ケース①:多方向交差点での信号の誤認
複数の信号機が同時に視野に入り、誤って対向車用の青信号や隣接レーンの矢印を見て発進するケースが多く見られます。
予測の視点:
・交差点に近づく前に「自分の進行方向の信号はどれか?」を目視で確認しておく
・斜めに設置された信号は“他車線用”である可能性を常に意識する対策
・交差点手前では必ず減速し、車線の中央で一時的に判断の時間を作る習慣をつける
🔸ケース②:人と自転車の不意の横断
スクランブル交差点や駅前の人通りが多い場所では、信号が青でも人や自転車が急に進入してくるリスクがあります。
予測の視点:
・横断歩道に向かって歩行者が“動きそう”な兆しをとらえる
・信号の色ではなく「歩行者の動き」に注意を集中させる対策
・青信号であっても“完全には信用しない”
・左右・前後の確認をしてから一呼吸おいて発進する
🔸ケース③:タクシー・バスの急停車・進路変更
駅前や繁華街では、バスやタクシーが突然停車・発進・進路変更することが多く、初心者にとっては予測しにくい代表的なリスクです。
予測の視点:
・バス停やタクシー乗り場の周囲では「すぐ動くかもしれない」と構えておく
・ウインカーがなくても車の挙動(徐行・ブレーキランプ)で予測する対策:
・車間距離を広くとる(1.5台分以上)  住宅街の交差点──買い物帰りの親子の不意な横断に備えて徐行運転する女性ドライバーの様子
住宅街の交差点──買い物帰りの親子の不意な横断に備えて徐行運転する女性ドライバーの様子
・追い越す際は歩道側の歩行者の動きにも注意を向ける
以下の項目に「はい/いいえ」で答えてみてください。 2つ以上「いいえ」があれば、実地トレーニングが強く推奨されます。
✅ 交差点で、自分の信号がどれかを即座に判別できる自信がある
✅ 青信号でも歩行者や自転車の動きを必ず確認している
✅ 駅前やバス停では、自車のスピードを落とし、停車車両の動きを予測している
✅ 信号や標識ではなく、“人の動き”に意識を向ける運転ができている
✅ 複雑な交差点では、焦らず「一拍置く」癖がある
これらのスキルは一朝一夕では身につきませんが、実際の交通環境でインストラクターと一緒に「予測力」を養うことで、驚くほど短期間で感覚を取り戻すことができます。 都市型の難所こそ、危険予測トレーニングの“本領”が発揮される場です。
【東京ドライビングサポートの駐車トレーニング】コインパーキング・商業施設での危険予測と接触事故を防ぐ実践対応
 住宅街の交差点──買い物帰りの親子の不意な横断に備えて徐行運転する女性ドライバーの様子
住宅街の交差点──買い物帰りの親子の不意な横断に備えて徐行運転する女性ドライバーの様子駐車場内は一見安全そうに見えますが、実は交通事故発生率が高いエリアの一つです。
特にペーパードライバーや運転ブランクのある方にとっては、狭い空間での判断や操作が重なり、接触・誤操作・ヒヤリとする場面が起こりやすくなります。
東京ドライビングサポートでは、コインパーキングや大型ショッピングモールの駐車場を想定した実践講習を行っています。
以下は、特に頻出する4つのリスクと、それに対する予測の視点・具体的な行動例です。
🔸ケース①:出庫直後の急な通行車との接触
コインパーキングから道路へ出る際、バックモニターだけを見て出庫し、後ろから来る車に接触する事故が多発しています。
予測の視点:
・ミラーやバックモニターだけでなく、頭をしっかり回して後方を直接目視する
・「今は車が来ていない」ではなく、「来る可能性がある」前提で動く対策
・出庫時は一度停止し、左右後方を再確認する習慣を徹底する
・ハザードランプ点灯+徐行で“出る意思”を周囲に伝える
🔸ケース②:狭い車室でのハンドル誤操作・接触
幅の狭いスペースに無理に駐車しようとして、寄りすぎやハンドル切り返し不足によるボディの擦れがよく見られます。
予測の視点:
・駐車前に「車室の幅」「隣の車との距離」「ドア開閉の余裕」があるかを判断する
・狭さを感じたら「1回で入れようとしない」意識が重要対策
・あらかじめ周囲に余裕がある車室を選ぶ(可能なら端や角の区画)
・切り返しを惜しまず、1回で決めようとしない
🔸ケース③:買い物客・子どもの不意の横断 特に週末の大型商業施設では、カートを押す買い物客や小さなお子さまが駐車区画内を自由に横断しており、視界外から突然現れることもあります。
予測の視点:
・「車が停まっている場所=人も出てくる可能性がある」と想定する
・店舗入り口やエレベーター付近、カート置き場付近は“飛び出し多発地点”と認識対策
・駐車場内も“道路と同じ”意識で、徐行+歩行者優先を徹底する
・停車中の車の影から出てくる“かくれ歩行者”を常に想像しておく
🔸ケース④:カーブミラー・交差路の死角 駐車場内のT字路や曲がり角では、死角から出てくる車との低速同士の接触事故が多発しています。
予測の視点:  住宅街の生活道路で子どもが飛び出してくるシーンを想定した実践トレーニング──「止まれる準備」が命を守る
住宅街の生活道路で子どもが飛び出してくるシーンを想定した実践トレーニング──「止まれる準備」が命を守る
・カーブミラーは確認するだけでなく、“相手に見せるため”にも活用する
・見えない角では「向こうからも来る」と仮定する対策
・交差部では一時停止+左右目視+クラクションで存在を知らせる
・歩行者や車の動きが活発な時間帯は、特に慎重に
📝 駐車場内での危険予測|セルフチェックシート 以下の項目に「はい/いいえ」で答えてください。 3つ以上「いいえ」の場合は、講習での実地練習が効果的です。
✅ 出庫時、ミラーとバックモニターだけでなく、目視でも確認している
✅ 狭い車室では「1回で入れる」より「安全に入れる」ことを優先している
✅ 駐車中も歩行者が飛び出してくる可能性を意識している
✅ 商業施設内では、カートや子どもの動きに特に注意している
✅ 駐車場の交差路では、必ず徐行・目視・クラクションの3点を意識している
駐車場はスピードが遅い分「油断しやすい場所」でもあります。
ですが、事故やトラブルの多くは「見えていなかった」のではなく「想像していなかった」ことが原因です。東京ドライビングサポートの実践講習では、こうした場面で“どう考えるか”“どう動くか”を、講師のアドバイスのもとで体感的に学ぶことができます。
🚗 危険予測に不安がある方へ──まずは無料相談から始めてみませんか?
運転中「どこを見ればいいかわからない」「とっさの判断が怖い」と感じている方に向けて、
東京ドライビングサポートでは、“危険予測”に特化した個別相談会を実施中です。
日常の運転シーンで不安に感じる場面をもとに、講師が丁寧にヒアリング・アドバイスいたします。
📘 実際の道で“予測する力”を鍛える90分間トレーニング
住宅街・生活道路・交差点など、事故が起こりやすい場所を走行しながら、
講師と一緒に「予測 → 判断 → 行動」を繰り返すトレーニングを行います。
実況中継形式や声かけ形式を取り入れ、机上では身につかない“実践力”をその場で体験できます。
【東京ドライビングサポートの住宅街講習】生活道路に潜む“見えない危険”を察知する予測力を養うトレーニング
 住宅街の生活道路で子どもが飛び出してくるシーンを想定した実践トレーニング──「止まれる準備」が命を守る
住宅街の生活道路で子どもが飛び出してくるシーンを想定した実践トレーニング──「止まれる準備」が命を守る住宅街は一見穏やかに見える反面、運転者の「油断」が事故につながりやすい場所です。
見通しの悪さ・道幅の狭さ・生活者の存在が重なるため、速度や判断ミスが即、出会い頭の事故や飛び出しに直結します。
東京ドライビングサポートでは、住宅街での危険予測をテーマに、「見えないリスクに気づく目線」と「正しい徐行・停止の習慣づけ」を軸にした実践講習を行っています。
以下に代表的な3つのケースと、それぞれの予測の視点と行動例をご紹介します。
🔸ケース①:子どもの飛び出し
夕方の下校時間帯や休日、子どもがボールを追いかけて突然道路に出てくるケースは後を絶ちません。
住宅街では、歩道が整備されていないため、子どもが車道を走っている場面も多く見られます。
予測の視点:
・公園や小学校の近くでは「いつでも子どもが飛び出してくる前提」で走行
・ブラインドになっている塀・植え込みの陰からの飛び出しを常に想定対策
・徐行運転+常にブレーキに足を添えておく
・窓を少し開けて生活音(子どもの声・自転車の音)を感じ取る  スクールゾーン 危険予測 横断歩道 子ども 住宅街 減速 注意力 ペーパードライバー講習
スクールゾーン 危険予測 横断歩道 子ども 住宅街 減速 注意力 ペーパードライバー講習
・夜間はハイビームを適切に活用し、照らしながら進む
🔸ケース②:無信号交差点での出会い頭事故
信号のない交差点は、どちらかが止まらなければ必ず接触する構造です。住宅街では見通しの悪い十字路やT字路が多く、突然他車が現れることも少なくありません。
・夜間はライトの配光に注意し、歩行者がいた場合は早めに減速 予測の視点: ・駐車車両を避ける際は反対車線に大きく膨らまないよう徐行で安全確保
・「止まっていない車が来るかもしれない」前提で自車が必ず止まる意識を持つ ・車体の陰やトランクが開いている車両は“人がいる可能性あり”と想定対策:
・フェンス・壁・駐車車両の死角から来る車両を“イメージで補う”習慣をつける対策 ・駐車車両の横を通るときは「その後ろから何かが出てくるかもしれない」意識を常に持つ
・一時停止 → 少し前に出て左右再確認 → 安全なら進行 予測の視点:
・交差点進入時は、速度ではなく「見える範囲」を基準にする
🔸ケース③:路上駐車の影からの自転車・人の飛び出し
住宅街は来客や住人の車による路上駐車が多く、それらの車の影に人や自転車が隠れている可能性があります。
夜間は特に視認が遅れやすく、接触リスクが高まります。📝 住宅街での危険予測|セルフチェックシート 以下の項目に「はい/いいえ」で答えてみてください。 2つ以上「いいえ」があれば、住宅街対策の実地トレーニングをおすすめします。
✅ 公園・学校の近くでは“子どもの飛び出し”を想定して徐行している
✅ 無信号交差点では、必ず停止し、左右を2回確認している
✅ 駐車車両の影に人や自転車がいる前提で運転している
✅ 夜間の住宅街では、ヘッドライトの使い方や速度に特に注意している
✅ 一時停止後、車体を前に出して再確認する癖がある
住宅街では「常に周囲に生活者がいる」ことを意識した運転が必要です。
予測の甘さは、低速でも取り返しのつかない事故につながることがあります。東京ドライビングサポートの講習では、住宅街特有の危険ポイントを一緒に走りながら丁寧に確認し、“身近な道こそ慎重に”を体感的に学ぶことができます。
【時間帯・曜日別の危険予測】平日と週末で異なる交通傾向に対応する実践的トレーニング|東京ドライビングサポート監修
 スクールゾーン 危険予測 横断歩道 子ども 住宅街 減速 注意力 ペーパードライバー講習
スクールゾーン 危険予測 横断歩道 子ども 住宅街 減速 注意力 ペーパードライバー講習運転中の危険は、場所だけでなく「時間帯」や「曜日」によっても大きく変わります。
同じ道路でも、平日朝の通勤時間と、週末昼のショッピングタイムでは、走っている車種も運転の雰囲気もまるで別物です。
東京ドライビングサポートでは、平日・週末それぞれの交通傾向に応じた予測力のトレーニングも重視しています。
以下に、それぞれの時間帯に応じた危険の特徴と、どのように備えるべきかをご紹介します。
🔸平日(特に朝夕)
傾向: 通勤車両・営業車・トラックが多く、目的地や時間に追われた“急ぎ気味”の運転が目立ちます。ウィンカーを出さずに右左折したり、強引な割り込みをしてくる車もあり、心理的にも周囲のスピード感に引っ張られやすくなります。
予測の視点:
・「周囲の車は急いでいる」前提で構える
・右左折のウィンカーは“出るのが遅い”“出さない”可能性を想定
・トラックの死角・左折巻き込み・急ブレーキに常に警戒対策:
・車間距離は常に広めにキープ(前後1.5台分以上)
・営業車やトラックには「入れ替わりが激しい」と認識し、前方を広く見ておく
・スクールゾーンでは標識だけでなく「子どもの気配」にも注意
🔸週末(土日・祝日) 傾向:
運転に慣れていないドライバーや、家族連れのマイカー、観光・レジャー目的の車が増えます。
駐車場待ち渋滞、突然の車線変更、狭い道での停車など、読めない動きが急に起こることも珍しくありません。
予測の視点:
・「周囲の車は不慣れかもしれない」「急な減速や停車がある」と仮定する
・小さな子どもを連れた歩行者が突然横断してくる可能性を意識
・観光地や公園周辺では歩行者と車が混在する状況に警戒対策:
・ショッピングモールや観光地周辺では“人の動き”を中心に見る
・駐車場待ちの車は無理に抜かず、ハザード点灯や譲り合いを意識する
・「状況が読めない前提」で、スピードではなく予測で走る  実際の交差点での危険予測トレーニング風景|東京ドライビングサポートでは現場を想定した実践講習を実施中
実際の交差点での危険予測トレーニング風景|東京ドライビングサポートでは現場を想定した実践講習を実施中 「信号は見えてるのに、判断が遅れてる気がした」──元営業ドライバーの声から見る、年齢とともに低下する“認知→判断→操作”の連携。
「信号は見えてるのに、判断が遅れてる気がした」──元営業ドライバーの声から見る、年齢とともに低下する“認知→判断→操作”の連携。  危険は“予測すれば回避できる”──住宅街で実地指導する小竿インストラクター(東京ドライビングサポート)イメージ
危険は“予測すれば回避できる”──住宅街で実地指導する小竿インストラクター(東京ドライビングサポート)イメージ
📝 平日・週末の運転傾向に対応できている?|セルフチェックシート 以下の質問に「はい/いいえ」で答えてください。 3つ以上「いいえ」がある場合は、曜日別対策のトレーニングをおすすめします。
✅ 平日朝は営業車・トラックの動きに注意して、車間距離を広く取っている
✅ ウィンカーが遅れる車がいることを前提に、自分の判断を急がないようにしている
✅ スクールゾーンでは「標識がなくても子どもがいる可能性」を常に考えている
✅ 土日は駐車場待ちや急停車の可能性を想定して、スピードを抑えている
✅ 公園やショッピングモール周辺では「車より人」を見る視点を持っている
曜日や時間帯によって道路の“空気”は変わります。
だからこそ、ペーパードライバーには「時間帯による危険の変化」を予測する力が欠かせません。東京ドライビングサポートでは、こうした変化に対応するトレーニングも取り入れており、平日朝・週末昼・夜間それぞれのリスクに応じた運転スキルを実践で身につけることができます。
🚗 危険予測に不安がある方へ──まずは無料相談から始めてみませんか?
運転中「どこを見ればいいかわからない」「とっさの判断が怖い」と感じている方に向けて、
東京ドライビングサポートでは、“危険予測”に特化した個別相談会を実施中です。
日常の運転シーンで不安に感じる場面をもとに、講師が丁寧にヒアリング・アドバイスいたします。
📘 実際の道で“予測する力”を鍛える90分間トレーニング
住宅街・生活道路・交差点など、事故が起こりやすい場所を走行しながら、
講師と一緒に「予測 → 判断 → 行動」を繰り返すトレーニングを行います。
実況中継形式や声かけ形式を取り入れ、机上では身につかない“実践力”をその場で体験できます。
【東京ドライビングサポートの危険予測トレーニング】“見えない危険”を読む力を育てる90分間の実践型講習とは?
 実際の交差点での危険予測トレーニング風景|東京ドライビングサポートでは現場を想定した実践講習を実施中
実際の交差点での危険予測トレーニング風景|東京ドライビングサポートでは現場を想定した実践講習を実施中東京ドライビングサポートが提供する90分間の危険予測トレーニング講習は、「なんとなく不安」「いつもヒヤッとする」と感じているペーパードライバーやブランクドライバーの方が、“未然に防ぐ力”=危険予測力を実地で身につけるための実践プログラムです。
この講習では、住宅街・市街地・商業施設周辺・交差点・駐車場など、あらゆる場面に応じて「何が起こりうるか」を考えながら走る力を育てます。
ただ車を動かすだけの練習ではなく、実況中継式の声かけとリアルタイム判断訓練を通して、事故を防ぐ判断力と反応力を鍛えていきます。
📘 講習の流れ(90分構成)
【STEP 1|ヒアリングとルート設計(10分)】 受講者の不安な場面やブランク年数を確認し、「住宅街」「複雑交差点」「駐車」「夜間運転」など、目的に合わせた実走ルートを組み立てます。 例:子どもを乗せて走る予定のある方は、生活道路・スクールゾーンを重点的に。 例:週末の商業施設で不安な方は、ショッピングモール周辺の渋滞・歩行者対策を。
【STEP 2|ウォームアップ走行(10〜15分)】 住宅街や交通量の少ない路地で、操作確認と視野の広げ方を実践。
ここでは「どこを見て、何を意識して走るか」を声に出しながら運転していただきます。
講師は受講者の目線・思考の癖を観察しながら、改善点をその場でフィードバック。
【STEP 3|危険予測トレーニング(55分)】 本講習の中核となるパート。以下のようなシーンを組み合わせて走行し、“危ない場所を想像して、行動に反映する”力を実地で養います。
🔹住宅街: 子どもの飛び出し/無信号交差点/路上駐車の影など、“生活道路”のリスクに対応。
👉 ブレーキに足を添えて走る・窓を開けて生活音を察知する訓練を実施。
🔹都市部・市街地: 多方向信号/スクランブル交差点/タクシー・バスの急停車などに対応。
👉 誤認信号を防ぐ視線の配分、車間距離と判断余白を取る技術を習得。
🔹駐車場(コインP・商業施設): 出庫時の後方確認/狭いスペースでの操作/歩行者との距離感を確認。
👉 ミラー+目視の切り替え、徐行時のハンドル操作を丁寧に繰り返し。
🔹週末・平日の交通傾向に応じた判断: 営業車両が多い朝、レジャー車両が多い昼間、それぞれに応じた車の流れの読み方を、実際の交通環境の中でトレーニングします。
【STEP 4|講評・フィードバック(5分)】 運転中の良かった点・改善点を丁寧にフィードバック。 「どのように予測できたか」「もし見落としていたらどうなっていたか」を振り返りながら、受講者一人ひとりに合った“次のステップ”を提案します。
🎯 本講習で得られる力 ・状況を“見てから反応する”のではなく、“想像して行動する”習慣
・事故を回避するための心構えと具体的テクニック
・緊張せず、余裕を持って判断する感覚
・講師との対話による安心感と、自分の運転を客観的に見る視点
📌 おすすめの方 ・10年以上運転しておらず、練習するにも怖さがある方
・事故経験や教習所でのトラウマがある方
・お子様の送迎や親の介護など、これから運転を必要としている方
・「自分が危ない運転をしてないか」を客観的に見直したい方
この90分の危険予測トレーニング講習は、ペーパードライバーを「もう一度運転できる人」へと導く、最初のステップとして多くの方に選ばれています。 安全な運転を取り戻すのは、恐怖を我慢することではなく、“先の危険を想像して備える力”を育てることから始まります。
【リアル受講者の声】判断の「間に合わなさ」を自覚して──危険予測トレーニングで変わった5人の走り出し
 「信号は見えてるのに、判断が遅れてる気がした」──元営業ドライバーの声から見る、年齢とともに低下する“認知→判断→操作”の連携。
「信号は見えてるのに、判断が遅れてる気がした」──元営業ドライバーの声から見る、年齢とともに低下する“認知→判断→操作”の連携。「なんか怖いけど、何が怖いのか自分でもわからない」 「大きな事故じゃなかったけど、あのときのヒヤッとがずっと残ってる」そんな感覚を胸に、東京ドライビングサポートの危険予測トレーニングを選ぶ方が増えています。
ブランク明けの方、高齢の方、家族に言われて気づいた方──
きっかけは様々ですが、どの方も「このままでは危ないかも」と気づいた“あの瞬間”がありました。今回は、受講者それぞれの背景や講習内容、そして講習後の気持ちの変化をリアルにご紹介します。
🔸40代女性/ブランク12年:「運転できた…けど、何が怖いかが分からなかった」
初回のお試し講習で「思ったより操作はできた。でも、自分の判断が正しいかがずっと怖かった」と話していた彼女。
2回目では無信号の住宅街交差点や、塾帰りの子どもが多い17時台の走行をリクエスト。
講師と一緒に“角の死角”や“音の先読み”を一つずつ拾っていくうちに、「ブレーキに足を添えたまま走る」「止まっても見えない場所は進まない」が自然に身につきました。
「頭でわかっていたことが、実際の現場で“行動”としてできるようになったのが嬉しい」と涙ぐんでいたのが印象的でした。
🔸70代男性/元営業ドライバー:「信号は見えてるのに、判断が遅れてる気がした」
「昔は1日200km走ってた。でも最近、“あれっ”て思うことが多くなって…」
そう話して申し込まれた男性。
講習ではバス通りでの横断歩行者、右折保護信号、片側1車線での路駐処理などを重点的に走行。
講師がリアルタイムで「今、何が見えました?」「この先、どんな可能性ありますか?」と問いかけることで、眠っていた“判断の回路”が再起動されたようでした。
「自分でも気づかなかった判断の甘さにゾッとした。でも、気づけてよかった」と語っていました。
🔸法人導入/人材会社 営業職:「運転スキルより、“事故を未然に防ぐ力”が必要だった」
営業で車を使う社員に対し、「いま事故を起こしたら会社の信頼が揺らぐ」と上長の判断でトレーニングを導入。
講習では実際に使用している社用車で、取引先ビルの駐車場への出入りや、早朝の裏道ルートを再現。 歩行者の飛び出し想定、車の死角、工事区域の徐行の仕方など、地図にはない“ヒヤリポイント”を洗い出しました。
「もし新人が何も考えずに走っていたら…」という気づきから、社内研修としての導入が進んでいます。
🔸30代女性/子育て中:「“その運転、怖いよ”って旦那に言われて…」
信号が青になると、周囲を見ずに一気に発進。
「急いでると、そこに人がいても気づかなかったかも」と講習中に自覚された場面もありました。
講師と一緒に都内のスクールゾーン・駅前ロータリー・信号の矢印付き交差点などを走りながら、“予測が1テンポ早くなる感覚”を掴んでいきました。
「家族を乗せても安心してもらえるようになった」と、自宅練習も始められたそうです。
🔸50代男性/経営者:「“事故は情報処理の失敗”だと気づいた」
「経営でも運転でも、“先が見える人間”がミスを防げる」
そう語り、自ら希望して講習を受講された男性。
講習では繁華街や右左折の集中する道路、複数の死角が絡む交差点を選び、一瞬ごとの“見え方”と“判断の分岐”を体感的に理解されました。
「無意識だった“思い込み運転”を見直せた」との言葉は、すべてのドライバーにとって響くものがあると感じました。
どの方も共通していたのは、「操作ではなく、“判断の質”が安全を決める」という実感。
東京ドライビングサポートの危険予測トレーニングは、経験や立場を問わず、「その人の視点」で走りを見直す90分です。
一歩踏み出すことで、“怖い”が“見える”に、“不安”が“備え”に変わっていきます。
🚗 危険予測に不安がある方へ──まずは無料相談から始めてみませんか?
運転中「どこを見ればいいかわからない」「とっさの判断が怖い」と感じている方に向けて、
東京ドライビングサポートでは、“危険予測”に特化した個別相談会を実施中です。
日常の運転シーンで不安に感じる場面をもとに、講師が丁寧にヒアリング・アドバイスいたします。
📘 実際の道で“予測する力”を鍛える90分間トレーニング
住宅街・生活道路・交差点など、事故が起こりやすい場所を走行しながら、
講師と一緒に「予測 → 判断 → 行動」を繰り返すトレーニングを行います。
実況中継形式や声かけ形式を取り入れ、机上では身につかない“実践力”をその場で体験できます。
危険は“予測すれば回避できる”──現場で磨いた小竿インストラクターの専門視点
 危険は“予測すれば回避できる”──住宅街で実地指導する小竿インストラクター(東京ドライビングサポート)イメージ
危険は“予測すれば回避できる”──住宅街で実地指導する小竿インストラクター(東京ドライビングサポート)イメージ 東京ドライビングサポートでは、元教習所の指導員であり、15年以上の指導歴を持つ小竿インストラクターが、危険予測トレーニングの全過程を監修・実施しています。
小竿インストラクターは、実際の道路で起こるヒヤリハットの傾向や再現性の高い事例を数多く現場で蓄積しており、単なる運転技術ではなく「危険の兆候をどこでどう察知するか」に重点を置いたトレーニングを構築しています。
都市部の混雑交差点での“信号の錯視”、住宅街での“音による予測”、駐車場での“死角判断”など──一人ひとりの運転環境や不安要素に合わせて、状況再現→指導→フィードバックを繰り返し、実際の運転で再現可能な危険察知力を高めていきます。
特に初心者や高齢者の方には、実況中継形式で「見える危険/潜むリスク」をリアルタイムで解説し、判断の“詰まり”が起きそうな瞬間をすばやく察知・介入。必要であれば停止後に状況を一緒に振り返りながら、「その瞬間に脳はどう反応していたか」まで一緒に言語化します。
これは心理的アプローチと交通工学的リスク認知を掛け合わせた、独自の“心理的カウンセリング型運転指導”でもあります。
事故は「不注意」ではなく、「予測不足」で起こる。
この信念のもと、東京ドライビングサポートの危険予測トレーニングは、未然に防ぐ力=予測力を育てることを最重視しています。 小竿インストラクターの専門性・経験・対話力が、その実践を可能にしています。
“あの時のヒヤリ”を忘れられないあなたへ──危険予測トレーニングを届けたい理由
運転に「慣れ」はあっても、「予測」がなければ安全は守れません。 私たち東京ドライビングサポートは、これまで数百名以上のペーパードライバーや高齢ドライバー、初心者の方と一緒に実走しながら、その“感覚”を痛感してきました。
「なんとなく運転してきたけど、あのとき子どもが飛び出していたら…」
「右折のタイミングで迷ってしまい、後ろからクラクションを鳴らされた…」
「駐車場で、出庫直後に自転車とぶつかりかけた」
それは、誰にでも起こりうる“ほんの一瞬の判断ミス”です。
でも、だからこそ──「その瞬間を予測し、備える力」を身につけてほしいと願っています。
この講習は、免許取得以来のブランクがある方、事故をきっかけに運転が怖くなってしまった方、家族を乗せて走るようになった親御さん、そして営業でお客様を乗せる責任を感じている社会人の方など、あらゆる立場の方に受けていただきたいトレーニングです。
危険予測は、交通標識を覚えることや、車庫入れが上手になることとは異なり、“自分と他者の命を守る”という意識のトレーニングです。
私たちはそれを、教科書ではなく現場で、一緒に考える時間を通じて、育てていきます。
このトレーニングを受けた方が「運転に対する意識が変わった」と口を揃えて語ってくださるのは、技術だけでなく“人としての意識”を更新する瞬間があるからです。
そしてその変化が、次に出会うかもしれない「ヒヤリ」を確実に減らすのです。
いま運転が怖いと感じているあなたも、
なんとなく不安を抱えたまま運転しているあなたも、
“自分の運転で誰かを守りたい”と思っているあなたも──どうか、90分のこの講習を、自分自身と向き合う時間として体験してみてください。
「まだ間に合う」
私たちは、その背中をそっと押す存在でありたいと願っています。
危険予測トレーニング講習に関するよくあるご質問(FAQ)
Q1. 危険予測トレーニングとは、どのような講習ですか?
危険予測トレーニングは、見通しの悪い交差点や横断歩道、住宅街などで「潜在的な危険」を事前に察知し、対応できる力を養う実践型の講習です。事故を防ぐための“気づく力”を重点的に身につけます。
Q2. 教習所で受けた内容とどう違うのですか?
教習所のカリキュラムでは“危険”が予測しやすい設定になっています。一方、当講習では実際の都内の道路を走行し、予測困難な場面やリアルなヒヤリハットを講師と一緒に体験しながら学びます。
Q3. どんな方が対象ですか?
運転にブランクがある方や、最近ヒヤリとした経験がある方、事故が怖くて再開に踏み切れない方に特におすすめです。また「自分は予測力が弱いかも」と感じている方にも向いています。
Q4. 具体的にどんなトレーニングをするのですか?
「一時停止」「飛び出しが起こりやすい場所」「右左折時の視野確保」などをテーマに、講師と一緒に実況中継のようなスタイルで現地を走行します。状況の“読み方”と“判断力”を同時に鍛えます。
Q5. 車両はマイカーでも受けられますか?
はい、マイカーでも可能です。ご自身の車両で練習することで、普段乗る環境での危険予測力を高めることができます(保険加入状況を確認の上、実施します)。
Q6. 90分で本当に変化が感じられますか?
多くの方が「視野の取り方が変わった」「怖さよりも注意力が上がった」と体感されています。90分という短時間でも、集中して体験すれば十分な変化を感じられる講習です。
Q7. 危険な場所ばかり走るのですか?
危険というよりも、「注意が必要な場面」を選んで走行します。講師が事前にルートを設計し、安全を確保した上で練習しますのでご安心ください。
Q8. 高齢者でも受講できますか?
もちろん可能です。70代以上の受講者も多くいらっしゃいます。身体の負担や集中力の配分にも配慮しながら、無理なく受けていただける内容です。
Q9. 危険予測力はどのように鍛えられるのですか?
ただ“目で見る”だけではなく、「この先に何が起こるか」を想像する習慣が重要です。当講習では、講師からリアルタイムで声かけを受けながら、頭の中で“もしも”を考えるクセを身につけていきます。
Q10. この講習を受けると何が変わるのでしょうか?
多くの方が「周囲を見る意識が変わった」「先を読む力がついた」と話しています。結果として“怖さ”が減り、“安全への自信”が芽生える──それが最大の変化です。
🚗 危険予測に不安がある方へ──まずは無料相談から始めてみませんか?
運転中「どこを見ればいいかわからない」「とっさの判断が怖い」と感じている方に向けて、
東京ドライビングサポートでは、“危険予測”に特化した個別相談会を実施中です。
日常の運転シーンで不安に感じる場面をもとに、講師が丁寧にヒアリング・アドバイスいたします。
📘 実際の道で“予測する力”を鍛える90分間トレーニング
住宅街・生活道路・交差点など、事故が起こりやすい場所を走行しながら、
講師と一緒に「予測 → 判断 → 行動」を繰り返すトレーニングを行います。
実況中継形式や声かけ形式を取り入れ、机上では身につかない“実践力”をその場で体験できます。
出張型ペーパードライバー講習を手がける「東京ドライビングサポート」
記事監修:小竿 建(こさお けん)
教習指導員資格者証(普通) / 教習指導員資格者証(普自二)
運転適性検査・指導者資格者証 保有
長年にわたり自動車教習所の教習指導員として、多くのドライバーの育成に携わる。
警察庁方式運転適性検査の指導者として、運転者の特性に応じた安全運転指導にも従事。
令和元年には、長年の交通法規遵守と安全運転励行、交通事故防止への貢献が認められ、
練馬警察署長および練馬交通安全協会会長より感謝状を贈呈。
豊富な指導経験と高い安全運転意識に基づき、この記事の内容を監修しています。
本記事の企画・取材・構成について
本記事は、東京ドライビングサポートの広報・マーケティングチームによる現場取材と分析をもとに構成されています。
取材・企画・構成を担当したのは、広報ディレクター 板倉 智(いたくら さとし)。
これまで数多くの受講者にインタビューを重ねてきた板倉は、SNS運用やSEO対策にも精通し、
「伝わる・検索される・信頼される」広報・情報発信を推進しています。
【店舗名(Name)】 東京ドライビングサポート|出張ペーパードライバー講習・高齢者講習サポート
【住所(Address)】 〒175-0092 東京都板橋区赤塚4丁目18-8
【電話番号(Phone)】 0120-763-818
【営業時間】 毎日 9:00〜20:00(年中無休)
※講習スタートは9時〜/最終講習は19時台まで対応可能です。
【対応エリア】 板橋区・練馬区・北区・和光市・朝霞市などを中心に出張対応
東京23区無料出張
【メールでのお問い合わせ】 info@tokyo-driving-support.jp
【講習予約はこちら】 ▶ 初回90分お試しコースを予約する(TimeRex)


