東京ドライビングサポート
メディア
お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。
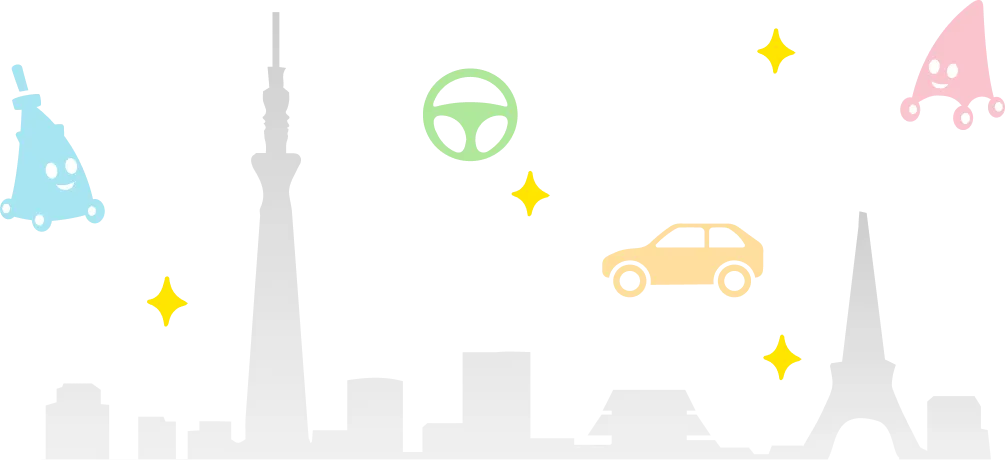
 「夫に教わると安心と思っていたのに…」──緊張が積み重なり、うまくいかない夫婦の運転練習。
「夫に教わると安心と思っていたのに…」──緊張が積み重なり、うまくいかない夫婦の運転練習。「夫に教えてもらえば一番安心だと思っていたのに、気づけば毎回ピリピリして終わってしまう。」 「練習を頑張りたい気持ちはあるのに、怖くて思うように動けない。」 そう感じたことがある方は、決して少なくありません。 実際、ペーパードライバー講習に来られる多くの方が、「最初は旦那に教えてもらっていたけれど続かなかった」と話されます。
最初は夫に教えてもらっていたけれど…
 「最初は夫に隣に乗ってもらえば安心と思っていたのに…」──気づけば、毎回ピリピリして終わってしまう。
「最初は夫に隣に乗ってもらえば安心と思っていたのに…」──気づけば、毎回ピリピリして終わってしまう。「初回お試しコース90分|最短2分で予約完了」
「個別無料相談|生活ルート設計&プラン相談」
「電話で今すぐ予約・相談する」
運転がうまい=教えるのがうまい、ではない理由
 「運転が上手い人ほど、教えるのは難しい」──夫婦のリアルな“教える・教わる”のギャップを描いた一枚。
「運転が上手い人ほど、教えるのは難しい」──夫婦のリアルな“教える・教わる”のギャップを描いた一枚。| 比較項目 | プロインストラクター | 旦那さん(経験者) |
|---|---|---|
| 判断の基準 | 相手の心理状態と安全距離を優先して設計 | 自身の経験値と反射的判断を基準にアドバイス |
| 指導の目的 | 「なぜ怖いのか」を分析し、安心と再現性を高める | 「早く慣れてほしい」「できるようになってほしい」 |
| 伝え方 | 論理的・段階的に言語化して導く | 感覚的でスピード重視。結果を指摘しやすい |
| 感情の扱い | 冷静・客観的に感情を抑制しながら指導 | 焦りや心配が口調に出やすい(愛情ゆえ) |
| 教える力の源 | 観察・分析・心理理解 | 経験・感覚・勘 |
| 受講者の印象 | 「落ち着いて教えてもらえた」「怖くなかった」 | 「正しいけど怖い」「言い方がきつく感じる」 |
| 結果 | 自信と再現性が身につく | プレッシャーと緊張が残りやすい |
旦那のプライドを守りながら、上手にプロへバトンタッチする方法
 「もう夫には教わりたくない」──そう思っても、感情を整理して穏やかに話すことで前に進める。夫婦でのすれ違いを解消する第一歩。
「もう夫には教わりたくない」──そう思っても、感情を整理して穏やかに話すことで前に進める。夫婦でのすれ違いを解消する第一歩。| 観点 | 旦那さんの心理・行動 | 上手な受け止め方・バトンタッチ方法 |
|---|---|---|
| 教えたい気持ち | 「自分が守ってやりたい」「自分の方が経験がある」 という責任感と自負 | 「頼りにしてる」「あなたが言ってることは正しい」と伝え、 感謝を言葉にしてからプロ講習を提案する |
| プライドの部分 | 「自分の指導で上達してほしい」という想いが強く、 外部に任せると“自分の役割を奪われた”と感じることも | 「あなたの言ってた通りのタイミングをプロの人にも褒められたよ」と共有し、 間接的に評価を伝える |
| 言い方・口調 | 愛情ゆえに強く聞こえてしまう。「危ない!」など反射的な発言 | 否定せず、「あのとき焦っちゃった」と一度受け入れ、 後で「専門の人に教わるね」とやんわり切り替える |
| 学び方の違い | 経験で覚えているため、理屈で説明するのが難しい | 「プロは言葉で説明してくれるから理解しやすい」と、 相手を否定せずに理由を説明する |
| 役割の分担 | “先生”になろうとしてプレッシャーを感じやすい | 「今度は応援役でいてほしい」とお願いし、 “支える立場”に変えてあげる |
| 理想の関係性 | 教える側として指導したい気持ち | 応援・共感・労いの言葉で“安全パートナー”として関わる |
「初回お試しコース90分|最短2分で予約完了」
「個別無料相談|生活ルート設計&プラン相談」
「電話で今すぐ予約・相談する」
プロ講習で感じた「安心の違い」とは
 「最初の10分で“心を整える”」──プロのインストラクターが寄り添い、安心を取り戻す東京ドライビングサポートの講習風景。
「最初の10分で“心を整える”」──プロのインストラクターが寄り添い、安心を取り戻す東京ドライビングサポートの講習風景。| 比較項目 | 旦那さんとの練習 | 東京ドライビングサポートの講習 |
|---|---|---|
| 声かけのトーン | 焦りや不安が混ざり、つい強い口調に。 「今いけたのに」「そこ違う!」 | 穏やかで肯定的。「今の感じ、とてもよかったですよ」「次は少し早めに見てみましょう」 |
| 教え方の焦点 | “正しい動作”を求める指導。 ミスを防ぐことに意識が向きがち。 | “なぜそうなるか”を一緒に考える指導。 理解と再現性を重視。 |
| 失敗への対応 | 「また間違えた」「危なかった」と感情が出やすい。 | 「いい経験になりましたね」「次に活かせます」と前向きにフォロー。 |
| 雰囲気 | 緊張と沈黙。お互いに気を遣い、重い空気に。 | 穏やかで落ち着いた空気。間の取り方がうまく、安心して考えられる。 |
| 学びの方向性 | 「間違えないように」意識が強く、恐怖を伴う。 | 「理解して再現する」ことを重視し、安心感と達成感が残る。 |
| 講習後の気持ち | 疲労感と自信喪失。「やっぱり運転向いてないかも」と感じやすい。 | 安心と自信。「もう少し運転してみよう」と前向きな気持ちになる。 |
| 夫婦関係への影響 | 小さな言い合いが増え、会話が減ることも。 | プロに任せることで衝突がなくなり、 夫婦の空気が穏やかに戻る。 |
夫婦でうまくいく「教えない運転練習」という新しい選択肢
 「教えない運転練習」──夫が“先生”ではなく“サポーター”になることで、練習の空気が驚くほど穏やかに変わる。
「教えない運転練習」──夫が“先生”ではなく“サポーター”になることで、練習の空気が驚くほど穏やかに変わる。| 比較項目 | 従来の「旦那さんが教える練習」 | 新しい「教えない練習」 |
|---|---|---|
| 役割関係 | 夫=先生、妻=生徒。上下関係が生まれやすい。 | 夫=応援者、妻=挑戦者。協力関係として並ぶ。 |
| 雰囲気 | 焦りや緊張が高まりやすく、言葉が鋭くなりやすい。 | 落ち着いた空気の中で、自分のペースで練習できる。 |
| 感情の流れ | 注意される → 萎縮する → ミスが増える → さらに注意される。 | 励まされる → 安心する → 余裕が生まれる → 操作が安定する。 |
| 学びの質 | 「間違えないこと」に意識が集中し、恐怖記憶が残る。 | 「どうすれば上手くいくか」を考える余裕が生まれる。 |
| 夫の気持ち | 「どうしてできないんだろう」と焦りや苛立ちを感じやすい。 | 「プロに任せた方が安心だな」と気持ちに余裕が生まれる。 |
| 結果 | 練習のたびにお互いが疲れ、運転への苦手意識が強まる。 | 運転も会話も穏やかに。安心感が夫婦の信頼を深める。 |
怒られない環境が、自信を育てる
 「緊張の時間を乗り越えて、ようやく笑顔で乾杯。」──環境が変わるだけで、人はこんなにもリラックスできる。
「緊張の時間を乗り越えて、ようやく笑顔で乾杯。」──環境が変わるだけで、人はこんなにもリラックスできる。| 環境の違い | 旦那さんとの練習 | プロ講習(東京ドライビングサポート) |
|---|---|---|
| 空気感 | 緊張と焦りが生まれやすく、会話がぎこちない。 | 落ち着いた雰囲気の中で安心して試せる。 |
| 声かけの質 | 「違う」「危ない」と否定的な表現が多くなりがち。 | 「いいですね」「今のタイミング覚えておきましょう」と肯定的に導く。 |
| 心理的安全性 | ミスを恐れ、操作が固くなる。 | 失敗を分析材料として扱い、リラックスして再挑戦できる。 |
| 成長の実感 | 練習のたびに自信を失い、次への意欲が下がる。 | 「前よりできた」を積み重ね、自信と安定感が増す。 |
| 関係性への影響 | お互いに疲弊し、言葉数が減る。 | 運転を通して会話が増え、夫婦関係がやわらぐ。 |
「初回お試しコース90分|最短2分で予約完了」
「個別無料相談|生活ルート設計&プラン相談」
「電話で今すぐ予約・相談する」
「プロに任せてよかった」と思える瞬間
 「プロに任せて本当によかった」──講習後に生まれるのは、運転技術だけでなく“安心の余白”です。
「プロに任せて本当によかった」──講習後に生まれるのは、運転技術だけでなく“安心の余白”です。| 比較項目 | 旦那さんとの練習 | プロ講習(東京ドライビングサポート) |
|---|---|---|
| 指導の目的 | 早く上達させたい、危険を避けさせたいという“結果重視” | 不安を取り除き、自信を育てる“過程重視” |
| 声かけの内容 | 「なんでそうなるの?」「今いけたでしょ!」など焦りが伝わる | 「今のタイミングいいですね」「次は少し早めに試しましょう」と安心感を生む |
| 失敗の扱い方 | 否定的に受け取られやすく、恐怖心が残る | “学びの材料”として分析し、次のステップへ導く |
| 心理的な余裕 | 常に緊張し、操作が固くなる | 穏やかな口調と間で、安心して判断できる |
| 講習後の変化 | 「もう無理かも」と自信を失うことが多い | 「次は一人で走ってみよう」と自然に前向きになれる |
「運転の再開」は、夫婦の信頼を取り戻すチャンス
| 要素 | 夫婦での練習 | プロ講習(東京ドライビングサポート) |
|---|---|---|
| 信頼の形 | 「間違えないでほしい」という“守る信頼” | 「失敗しても大丈夫」という“支える信頼” |
| 関係性の構図 | 先生と生徒のような上下関係になりやすい | パートナーとして並走する“横の関係” |
| 感情の流れ | 注意 → 緊張 → 失敗 → 気まずさの連鎖 | 観察 → 共感 → 安心 → 成功体験の連鎖 |
| 学びの姿勢 | 「怒られないように」と防御的 | 「やってみよう」と主体的 |
| 夫婦への効果 | お互いに疲れ、会話が減りやすい | 「頑張ってるね」「ありがとう」と自然に言葉が増える |
50代女性の体験談 ― 夫との練習で挫折し、プロ講習で自信を取り戻した日
 「信頼を取り戻す時間」──プロのサポートがあれば、不安が少しずつ“自信”に変わっていく。
「信頼を取り戻す時間」──プロのサポートがあれば、不安が少しずつ“自信”に変わっていく。| 比較項目 | 旦那さんとの練習 | 東京ドライビングサポート(小竿インストラクター) |
|---|---|---|
| 教える雰囲気 | 最初は協力的だったが、回数を重ねるうちに 「今の違う」「なんでブレーキ踏んだの?」と厳しくなる。 | 「今日は無理せず、車と仲直りする日だと思ってください」と優しい声かけ。 始まりから終わりまで穏やかで落ち着いた空気。 |
| 練習中の心理 | 焦りと恐怖で体が固まり、注意されるたびに自信を失う。 「また怒られるかも」という不安が先に立つ。 | ミスしても「今の判断悪くないですよ」「次は少し早めに試しましょう」と前向きにサポート。 怖さよりも理解が残る。 |
| 教え方の違い | 経験に基づく感覚的な指導。 「もっと右!」「いけるいける!」など勢い重視。 | 具体的かつ論理的な指導。 「右ミラーに白線がこの位置に見えたらハンドルを切りましょう」など、再現性を重視。 |
| 講習後の気持ち | 毎回疲労感が残り、「もう運転は無理」と感じてしまう。 練習を続ける意欲が薄れる。 | 「運転が楽しい」と感じられるように。 終わった後も心地よい達成感と安心感が残る。 |
| 上達のスピード | 焦りが原因で進歩を実感できず、同じミスを繰り返す。 | 回数を重ねるごとに運転感覚を取り戻し、「できた!」の実感が増えていく。 |
| 夫婦関係の変化 | 練習のたびに喧嘩が増え、会話も減少。お互いに気まずい時間が増える。 | 「最近落ち着いて運転できてるね」と夫が笑顔に。 プロに任せたことで関係も穏やかに戻る。 |
| 最終的な変化 | 半年間運転を諦めるほど自信を喪失。 | 数回の講習で10年のブランクを克服し、「また一人で運転してみたい」と思えるように。 |
生活ルートを中心に4回の練習で取り戻した“自信と日常”
 「最終回は“実生活ルート”での仕上げ走行。」──緊張の中にも自信の表情が。
「最終回は“実生活ルート”での仕上げ走行。」──緊張の中にも自信の表情が。| 回数 | 練習ルート | 主な練習内容と成長ポイント |
|---|---|---|
| 第1回 | 自宅周辺〜最寄りスーパー | 最初は緊張が強かったため、車の操作と感覚を取り戻すことからスタート。 ハンドル操作、ブレーキの踏み方、交差点での一時停止など、「怖くない距離」での慣らし運転を中心に実施。 小竿インストラクターが細かく声をかけ、無理のないペースで“初日から成功体験”を作ることを意識しました。 |
| 第2回 | 自宅〜駅前・ドラッグストア | 実際の生活動線を想定し、信号の多い交差点や右折・左折の練習を重点的に実施。 見通しの悪い角での「安全確認の習慣化」や、歩行者・自転車への意識配分を指導。 この頃から「運転している感覚が戻ってきた」と笑顔が増え始めました。 |
| 第3回 | 自宅〜ショッピングモール・主要道路 | 第3回では、やや交通量の多いルートへステップアップ。 合流や車線変更、駐車場でのバック操作など、「判断力と空間感覚」を鍛える実践トレーニングを実施。 小竿インストラクターが「焦らず、呼吸して確認してから動きましょう」と声をかけ、冷静に対処できるようサポートしました。 |
| 第4回 | 自宅〜病院・学校・スーパー複合ルート | 最終回は、“実際の生活を再現したルート走行”。 目的地を複数設定し、信号のない交差点・住宅街・狭い道などを組み合わせて練習。 小竿さんの的確なナビゲーションで、最後には自分一人でもスムーズに走行できるように。 「もう助手席に夫を乗せても大丈夫かも」と笑顔で話す姿が印象的でした。 |
編集後記 ― 「もう運転が怖くない」女性から届いた嬉しい報告
 「怖かった運転が、今は旅の楽しみに。」──夕日の沖縄で迎える、再出発の瞬間。
「怖かった運転が、今は旅の楽しみに。」──夕日の沖縄で迎える、再出発の瞬間。「初回お試しコース90分|最短2分で予約完了」
「個別無料相談|生活ルート設計&プラン相談」
「電話で今すぐ予約・相談する」
Q1. 旦那さんに教えてもらってもうまくいかないのですが、プロ講習に変えると違いますか?
Q2. 免許を取ってすぐでも受講可能ですか?
Q3. 旦那が横に乗ると緊張してしまいます。講習では一人で練習できますか?
Q4. 教えるのが苦手な夫に代わって、優しく指導してもらえますか?
Q5. 長年ブランクがあると、運転感覚は取り戻せますか?
Q6. 一度挫折してから半年以上経っています。それでも大丈夫ですか?
Q7. 担当インストラクターは選べますか?
Q8. 最初の練習はどんな内容から始まりますか?
Q9. 運転中に怒られることはありませんか?
Q10. 教習所のように厳しく注意されることはありますか?
Q11. 講習の回数はどのくらい必要ですか?
Q12. 自分の車で練習できますか?
Q13. 狭い住宅街やスーパーの駐車も練習できますか?
Q14. 家の近くの道を一緒にルート設計してもらえますか?
Q15. 女性の受講者は多いですか?
Q16. 夫婦関係がぎくしゃくしても講習を受けて大丈夫ですか?
Q17. 家族に内緒で受講することはできますか?
Q18. 雨の日でも講習は行われますか?
Q19. 1回の講習時間はどれくらいですか?
Q20. 同じインストラクターが担当してくれますか?
Q21. 一人での運転が怖くなくなるまで、どれくらいかかりますか?
Q22. 旦那が付き添い見学しても大丈夫ですか?
Q23. 駐車が特に苦手です。重点的に練習できますか?
Q24. 講習後にマイカーを購入しても大丈夫ですか?
Q25. 旅行先(沖縄など)で運転できるようになりますか?
Q26. 家族に「最近変わったね」と言われる人もいますか?
Q27. 講習はどの地域まで来てもらえますか?
Q28. 講習後のフォローアップはありますか?
Q29. 怒られずに練習したい人に向いていますか?
Q30. 最後に受講を迷っている方へ一言ありますか?


