ホーム
東京ドライビングサポートメディア
東京ドライビングサポート
メディア
お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。
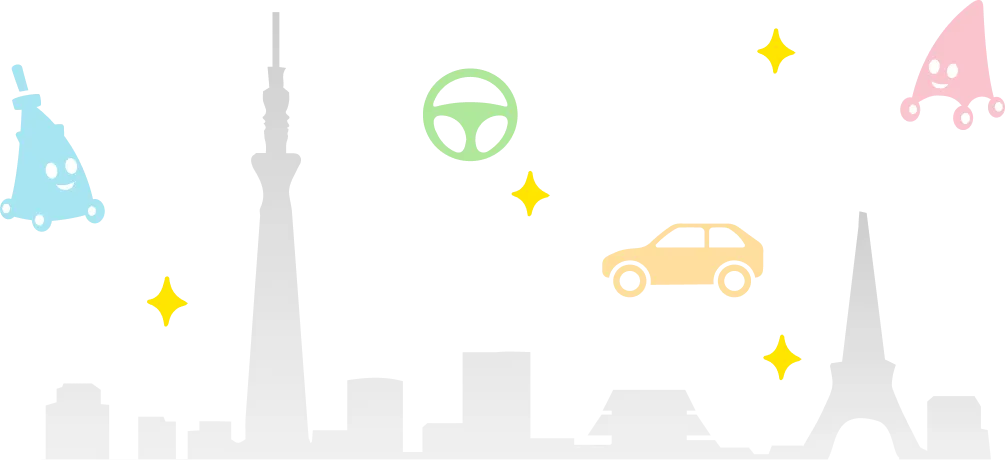
都内で高齢者講習を受けられるおすすめ教習所5選【2025年最新版】
 東京で高齢者向け運転講習を検討中の方へ|実際に教習所に通うシニア男性のイメージ
東京で高齢者向け運転講習を検討中の方へ|実際に教習所に通うシニア男性のイメージ
「免許更新の案内と一緒に届いた“高齢者講習”って、何をするのかよくわからない」
「東京都内で安心して受けられる教習所は、どこを選べばいいのか不安」 こうした疑問や不安を抱えている高齢ドライバーや、そのご家族の方は少なくありません。 特に初めて高齢者講習を受ける方にとっては、 講習内容・所要時間・適性検査の詳細がわからず、気持ちが重くなるのも当然です。 本記事では、東京都内で高齢者講習を受ける方に向けて、以下の情報をわかりやすく解説します: ・高齢者講習の目的と内容 ・必要な書類や準備すべきこと ・東京都内で予約しやすい教習所の選び方 ・評判の高い教習所5選(2025年最新版) 講習の流れや受け方を事前に理解しておくことで、
「慌てず」「迷わず」「落ち着いて」受講できるようになります。 この記事を通して、ご自身またはご家族にとって最適な教習所を見つけ、
大切な免許の更新手続きをスムーズに進めていただければ幸いです。
【2025年版】高齢者講習の内容と対象年齢・条件とは?受講の流れと準備すべきポイントを解説

高齢者講習は、70歳以上の方が運転免許を更新する際に義務づけられている重要な制度です。
これは、加齢に伴う運転能力や認知機能の変化に対応するための安全対策として、道路交通法に基づいて実施されています。 特に東京都内の指定教習所では、高齢者講習に特化したカリキュラムやサポート体制が整備されており、初めて受講する方でも安心して講習を受けられるようになっています。 このセクションでは、以下のような高齢者講習に関する基本的な流れと手続きを分かりやすくまとめました:
- 高齢者講習の対象年齢は?(70歳から段階的に変化)
- 案内通知はいつ届く?(更新時期に応じてハガキで届く)
- 講習の予約方法は?(電話・インターネット・教習所窓口など)
- どこで受ければいい?(都内の指定自動車教習所一覧)
高齢者講習の対象年齢は何歳から?免許更新で受講が必要になる条件と注意点
高齢者講習とは、70歳以上のドライバーが免許更新時に必ず受けなければならない法定の講習です。
通常の免許更新とは異なり、70歳を超えると道路交通法に基づきこの講習の受講が義務化されており、講習を完了しなければ免許の更新はできません。 さらに75歳以上になると、追加で「認知機能検査」の受検も必要になります。
この検査結果に応じて、受講する講習の内容が以下のように変わるのが特徴です。
- 記憶力や判断力に問題がない場合 → 一般的な講習のみ
- 記憶力・判断力に低下の兆しがある場合 → より詳細な運転技能講習が加わる
高齢者講習の通知ハガキが届いたら?予約から当日の流れまでをわかりやすく解説
高齢者講習の案内は、運転免許証の有効期限満了日の約6か月前を目安に、「高齢者講習等のお知らせハガキ」として警察(公安委員会)から郵送されます。 この通知ハガキには、以下のような受講手続きに関する重要な情報が記載されています。
- 認知機能検査が必要かどうか
- 受講すべき高齢者講習の種類(一般講習・特定講習・運転技能講習)
- 予約方法(電話・Web予約の案内)
- 受講期限と申込締切
高齢者講習の予約方法と注意点|スムーズに受けるための手順を徹底解説
高齢者講習の予約は、通知ハガキに記載されている指定自動車教習所に電話するのが一般的な方法です。
最近では、インターネット予約に対応した教習所も増えており、スマートフォンやパソコンからスムーズに申し込むことも可能になっています。 ただし、午前中や土日の時間帯は予約が集中しやすく、特に東京都内の人気教習所ではすぐに満席になることもあります。
そのため、通知ハガキを受け取ったらできるだけ早めに予約を行うのがポイントです。 予約手続きをスムーズに進めるために、以下の情報を事前に確認しておきましょう: ・認知機能検査の受検が必要か(75歳以上の方が対象) ・受講すべき講習の種類(一般講習・特定講習など) これらの情報を間違えて伝えてしまうと、当日に受講できない・再予約が必要といったトラブルに発展する恐れがあります。 予約前には必ずハガキの内容をよく確認し、正確な情報をもとに手続きを行うことで、安心・安全に高齢者講習を受講することができます。
高齢者講習の予約はどうする?電話・Web予約の流れと注意点をわかりやすく解説
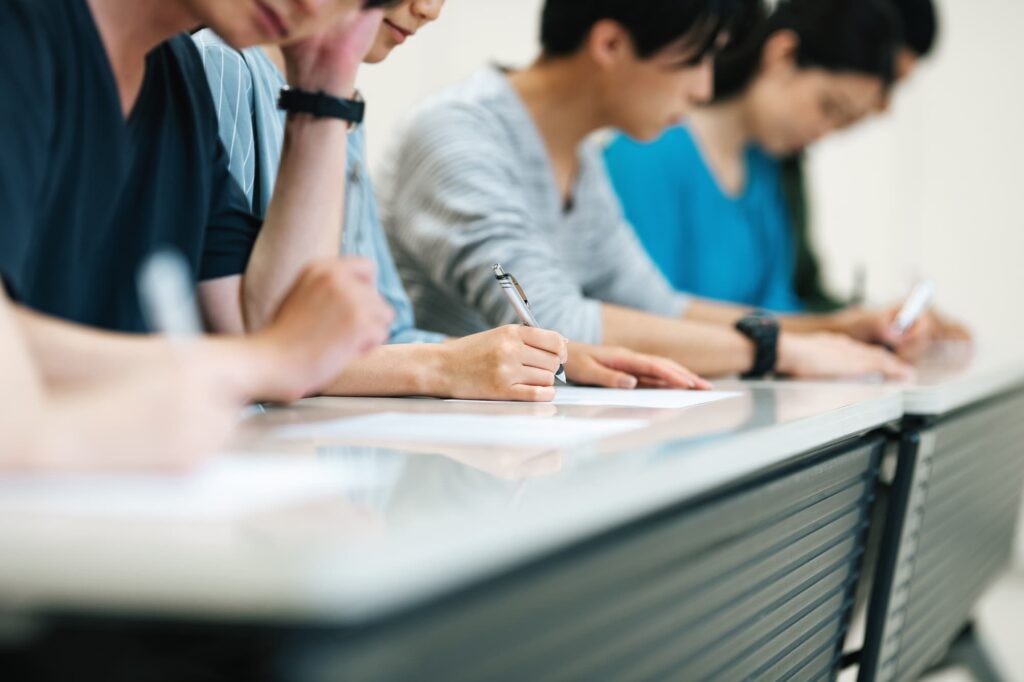
高齢者講習は、運転に必要な知識や技能を再確認し、これからも安全に運転を続けるために設けられた、免許更新時に必須の制度です。 特に初めて高齢者講習を受ける方にとっては、内容がわからないまま当日を迎えることに不安を感じるケースも少なくありません。 事前に講習の内容や所要時間、必要な持ち物を確認しておくことで、当日の心配を軽減し、落ち着いて受講することができます。 このセクションでは、高齢者講習の種類(一般講習・特定講習・運転技能講習)ごとに異なる座学・実技・適性検査の内容や、所要時間の目安を詳しく解説します。 はじめての方にもわかりやすく整理していますので、受講前にぜひチェックしておきましょう。
高齢者講習の実車指導・適性検査の内容とは?講習当日の流れとポイントを解説
高齢者講習の中で最初に行われるのが、座学(講義形式)です。
このパートでは、最新の交通ルールや道路標識の再確認、高齢ドライバーに多い運転ミスの傾向、安全運転のポイントなどを学びます。 ただ講師の話を聞くだけでなく、配布された教材をもとに簡単な確認テストが行われる場合もあります。
また、加齢による認知機能や身体機能の変化に応じて注意すべき点についても丁寧に解説されるため、「これからの運転」に必要な知識を客観的に見直す機会となります。 座学講習の所要時間の目安は以下のとおりです:
・一般講習の場合:約1時間 ・特定講習の場合:約1.5時間(座学+実技を含む) 受講する講習の種類や受講人数によって所要時間に多少の違いはありますが、座学は高齢者講習の中でも特に重要な時間です。
年齢や経験に関係なく、自分自身の運転を客観的に振り返る貴重な機会といえるでしょう。
高齢者講習の実技講習と適性検査とは?当日の流れと注意点をわかりやすく解説
講義の後には、実車による運転技能の確認(実技)と、各種の適性検査が行われます。
これらは、運転を継続するにあたり、現在の運転操作能力や判断力を客観的に把握するための重要な工程です。 高齢者講習では、座学に続いて実技講習(実車指導)と適性検査が行われます。
このパートでは、実際の運転感覚や身体機能をチェックし、安全運転を続けるためのポイントを確認します。 ■ 実車指導の内容 教習所内のコースを使用して、以下のような基本操作と安全確認がチェックされます。 ・発進・停止、ウインカー操作の正確さ ・交差点での左右確認・巻き込み確認 ・後方確認を含むバック駐車のハンドル操作 ・道路標識や交通ルールの遵守状況 これらを通じて、日常運転での運転感覚の維持と安全意識の確認が目的となります。 ■ 適性検査の内容 専用の機器を使って、以下の項目が測定されます。 ・視力・夜間視力 ・動体視力(動くものを正確に捉える能力) ・判断力・反応速度(信号や障害物への対応の速さ) 検査結果は講師から個別にフィードバックがあり、今後の運転で注意すべき点やアドバイスが伝えられます。 ■ 所要時間の目安 ・実技・適性検査の所要時間:約1時間〜1時間半 ・全体の講習時間(座学含む):約2〜2.5時間(教習所によって差あり)
高齢者講習に合格・不合格はある?評価基準と講習の目的をわかりやすく解説
高齢者講習には、一般的な試験のような合格・不合格の判定はありません。
講習の本来の目的は、運転への意識を再確認し、安全に運転を続けるための知識と技術を見直すことにあります。 講習を受講し終えると、「高齢者講習修了証明書」が発行されます。
この証明書を免許更新時に提出することで、正式に更新手続きを進めることができます。 仮に適性検査や実技講習中に「注意が必要」と判断されたとしても、免許が失効・取り消しになることはありません。
再受講を求められるケースは基本的になく、講師からは個別に今後の運転に関するアドバイスや注意点が丁寧に伝えられます。 つまり、高齢者講習とは「合格のための試験」ではなく、今後の運転を安心して続けるための“学び直しの場”なのです。
過度に身構える必要はありませんが、形式的に受けるのではなく、自分自身の運転を見つめ直す前向きな機会として捉えることが大切です。 東京都内の指定教習所では、丁寧で分かりやすい高齢者講習が行われています。
不安な方は、事前に講習内容や所要時間をしっかり確認して、安心して受講日を迎えましょう。
東京で高齢者講習に対応した教習所おすすめ5選|評判・予約のしやすさ・対応力で比較

高齢者講習は全国の指定自動車教習所で受講可能ですが、東京都内で講習を受ける場合は「アクセスの良さ」「予約のしやすさ」「講習対応の質」が重要な判断基準になります。 この記事では、実際の受講者からの評価や対応の丁寧さ、予約の取りやすさなどをもとに、東京都内で高齢者講習に対応しているおすすめの教習所を5つ厳選してご紹介します。 初めて講習を受ける方や、ご家族のサポートを検討している方にも参考になる内容です。
東京ドライビングサポート|出張対応&個別指導で安心の高齢者講習を提供
東京都内で柔軟な対応力と個別指導の丁寧さが高評価を得ている教習所が「東京ドライビングサポート」です。 高齢者講習にも対応しており、一人ひとりに寄り添ったマンツーマン指導と、わかりやすく実用的な座学が特長です。 特に注目されているのが、自宅周辺や希望ルートで実施できる出張型講習のスタイル。 外出に不安があるシニアドライバーや、運転に長いブランクがある方にも安心して受けていただける設計となっています。 また、事前の無料相談によりスケジュールの柔軟な調整が可能な点も、他の教習所にはない魅力の一つです。 「講習が不安」「遠出は難しい」といった声にもしっかり応え、親身なカウンセリング型サポートで信頼を集めています。 ご本人だけでなく、ご家族からの相談や事前の問い合わせにも対応しており、 東京で高齢者講習を受ける際の安心できる選択肢としておすすめです。武蔵境自動車教習所|安心のサポートと静かな環境で評判の高齢者講習
東京都武蔵野市にある武蔵境自動車教習所は、高齢者講習における丁寧な対応と安心できる教習環境で、多くの高評価を集めている教習所です。 講習の前には、当日の流れや必要な持ち物の説明がしっかりと行われ、実技講習も落ち着いた教習コースで実施されるため、久しぶりの運転に不安がある方でも安心して取り組める環境が整っています。 さらに、アクセスの良さやWeb予約のしやすさ、スタッフの親切な案内など、初めて高齢者講習を受ける方にも優しい工夫が多く備わっています。 口コミでも「説明がわかりやすく安心できた」「スタッフがとても親切だった」などの声が多数あり、信頼して任せられる教習所として、武蔵野エリアで高い人気を誇っています。飛鳥ドライビングカレッジ東京|設備充実で便利な講習体制が魅力の教習所
東京都練馬区にある飛鳥ドライビングカレッジ東京は、高齢者講習にも対応した大型自動車教習所として知られ、受講実績や対応件数も年々増加しています。 オンラインで仮予約ができる仕組みが整っており、事前にスケジュールを確認・調整しやすい点は大きなメリットです。 施設内は清潔感があり、受付や案内も比較的スムーズで、利便性重視の高齢ドライバーから高評価を得ています。 一方で、受講者数が多いため、繁忙期は予約が取りづらいケースもあり、人によってはやや事務的に感じる対応に不安を覚えることもあるかもしれません。 とはいえ、講習内容・設備の充実度は非常に高く、便利さや機能性を重視する方にとってはおすすめの教習所です。 東京都内で高齢者講習をスムーズに受けたい方には、選択肢の一つとして検討する価値があります。日の丸自動車学校|ベテラン講師と柔軟な対応が魅力の教習所(目黒区)
東京都目黒区にある日の丸自動車学校は、高齢者講習に対応した体制と、経験豊富な講師による落ち着いた実技・座学指導が好評の教習所です。 窓口の案内や予約時の対応も丁寧で、アクセスの良さやスケジュール調整の柔軟さが、初めて高齢者講習を受ける方にも安心と評価されています。 また、高齢者講習専用の時間帯・日程が設定されている時期もあり、集中して受けたい方や短期間で完了させたい方には非常に便利な環境です。 一方で、施設全体はややコンパクトなため、混雑時には待ち時間が発生する可能性もあります。 受講当日は時間に余裕を持って訪問するのがおすすめです。京成ドライビングスクール|広い敷地と充実設備が魅力の老舗教習所(葛飾区)
東京都葛飾区にある京成ドライビングスクールは、高齢者講習に対応した老舗の大型教習所として、多くのドライバーから信頼を集めています。 敷地が広く、最新の設備を備えた講習環境で、高齢者講習では基本に忠実でわかりやすい座学と、落ち着いて取り組める実車教習が提供されています。 無料の送迎バスが利用可能で、受付・案内も丁寧な対応が期待できるため、地域密着型の信頼感も強みです。 一方で、受講者数が多く事務的な印象を受けることがあるという声や、柔軟な個別対応がやや少ないという口コミも見受けられます。 そのため、「初めての講習で丁寧なサポートを重視したい方」よりも、「設備の整った環境で効率よく受講したい方」におすすめの教習所です。高齢者講習の教習所選びで失敗しないためのポイントと注意点【東京都内対応】
東京都内には高齢者講習に対応した自動車教習所が多数ありますが、「どこを選べば安心なのか分からない」「せっかく予約したのに対応に不満があった」という声も少なくありません。特に初めて高齢者講習を受ける方にとって、教習所選びは不安の大きな要因となりがちです。 ここでは、東京都内で高齢者講習に対応した教習所を選ぶ際に重視すべき3つのポイントをわかりやすく解説します。 ① 通いやすさとアクセスの良さを確認する 高齢者講習は2〜3時間に及ぶケースが多く、慣れない場所への移動は体力的な負担にもなりかねません。最寄り駅から徒歩圏内であるか、バス路線が充実しているかといったアクセスの利便性は、教習所選びで最も基本となる視点です。 また、東京都内には送迎バスのある教習所もあり、こうしたサポート体制が整っているかどうかもチェックポイントになります。 ② 講師の対応や講習の評判を確認する 高齢者講習では、加齢による身体の変化や不安に寄り添った丁寧な指導が求められます。そのため、「教官の説明が分かりやすかった」「落ち着いて講習を受けられた」といった口コミは、安心して受講できるかどうかの大きなヒントになります。 Googleマップやレビューサイトで「高齢者講習 対応」などのキーワードで検索し、実際の受講者からの評価を確認することをおすすめします。 ③ 費用やキャンセルポリシーも事前に把握 高齢者講習の料金は、教習所によって5,000円〜8,000円程度とばらつきがあります。また、予約変更やキャンセル時の対応も教習所によって異なるため、「当日キャンセルで全額負担」といった事態にならないよう、予約前に公式サイトで詳細を確認しておきましょう。 とくに東京都内では人気のある日時が早期に埋まりやすいため、予約ルールや支払い条件を含め、スムーズに受講できる体制が整っているかは非常に重要です。
高齢者講習を受ける前に準備しておくべきこととは?当日安心して臨むための3つのポイント
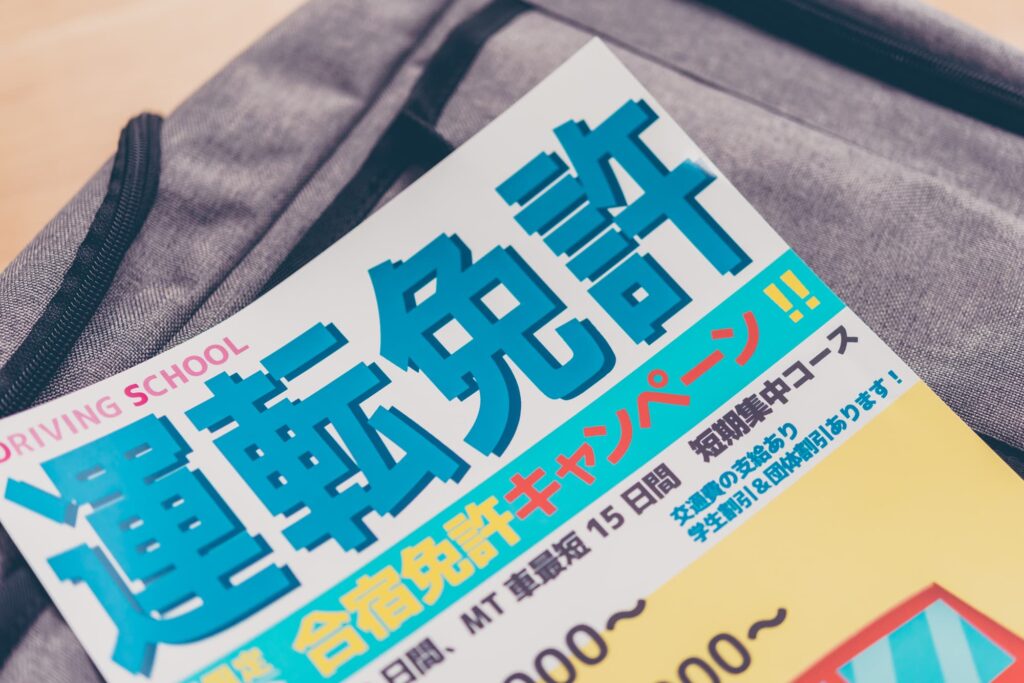
高齢者講習を受ける前に準備しておくべきこととは?当日安心して臨むための3つのポイント
高齢者講習を安心して受講するためには、事前の準備がとても重要です。
忘れ物や体調不良などで受講できなかった…という事態を防ぐためにも、 必要な持ち物や当日の注意点をしっかり確認しておきましょう。 必要書類や持ち物の確認 必ず持参すべきものは以下の通りです:
- 講習の案内ハガキ
- 運転免許証
- 筆記用具
- 眼鏡や補聴器などの補助具(必要な方)
高齢者講習のよくある質問と不安の解消法|受講前に知って安心
高齢者講習を初めて受ける方にとっては、手続きや内容についての不安がつきものです。
ここでは、よく寄せられる質問に対して、丁寧に解説していきます。
事前に疑問を解消することで、落ち着いて講習に臨むことができます。
講習に落ちたらどうなる?再受講の流れ
高齢者講習に「合格・不合格」という判定は基本的にありません。
ただし、講習の一環である適性検査の結果が著しく悪い場合や、指導員の判断によっては、追加講習が必要とされることがあります。
このようなケースでは、教習所から再講習の案内が届くので、指示に従って再受講を行う必要があります。
ただし、ほとんどの方が1回の受講で終了できるため、過度に心配する必要はありません。
免許返納と講習の関係は?
免許の自主返納を検討している方にとって、高齢者講習を受けるべきかどうか悩むこともあるでしょう。
基本的には、運転を今後も継続する意思がある方が講習の対象となります。
もし、講習の案内ハガキが届いた後に返納を決めた場合でも、講習を受けずに運転免許センターや警察署で返納手続きを行うことが可能です。
また、返納によって「運転経歴証明書」が交付される制度もあり、身分証明として有効に活用できます。
親の代わりに予約・付き添いは可能?
高齢の家族が講習を受ける場合、予約の手続きや当日の付き添いが必要になることもあります。
予約は、本人に代わって家族が電話をかけたり、教習所の窓口で手続きを行うことが可能です。
また、当日も教習所によっては送迎の付き添いや、受付までの同行が認められている場合があります。
事前に教習所に相談しておくことで、スムーズな対応が受けられます。
東京都で高齢者講習を受けるなら?安心できる教習所選びの総まとめ

高齢者講習は、加齢による身体機能の変化を確認し、安全運転を続けるための大切な機会です。 これからも自信を持ってハンドルを握るために、自分に合った教習所選びが何より重要です。 ここでは、失敗しないための選び方のポイントと、家族とも安心して準備を進めるための視点をお伝えします。
失敗しない教習所選びのポイントとは
高齢者講習を受けるうえで教習所選びは非常に重要です。特にアクセスの利便性と講習時の対応の丁寧さは、当日のストレスや不安を大きく軽減します。
講習は1日で終わることが多いものの、教習所までの移動が負担にならないことや、スタッフが高齢者に慣れており優しく対応してくれるかどうかが、安心感に直結します。 また、予約の取りやすさも見逃せないポイントです。特に人気のある時期にはすぐに予約が埋まってしまうため、ネットや電話予約がしやすく、日程の融通が効く施設を選ぶとスムーズです。
実際に受講した方の口コミや、Googleレビューなどを活用して、信頼できる教習所を見極めましょう。
家族と一緒に不安を取り除く準備を
初めて高齢者講習を受ける方にとって、流れや必要な持ち物など不明点が多く、不安になってしまうこともあります。
そんなときは、ご家族がサポート役として一緒に準備を進めるのがおすすめです。 予約手続きや送迎のサポートはもちろん、事前の情報収集や確認事項を一緒に整理するだけでも、受講者にとっては大きな安心材料になります。
講習は決して難しいものではなく、ほとんどの教習所がリラックスした雰囲気で進行してくれるため、過度な心配は不要です。 講習を「運転をこれからも安全に続けるための前向きなきっかけ」と捉え、ご家族と一緒に準備を進めることが、安心して受講する第一歩になります。
まずは「初回お試しコース(90分)」から始めてみませんか? 今なら無料で出張対応!不安を相談しながら受けられます。▶ 初回お試しコースの詳細を見る ▶ 受講者のリアルな体験談を読む
👤 監修:東京ドライビングサポート/インストラクター 小竿 建
本記事は、出張型ペーパードライバー講習を手がける「東京ドライビングサポート」
記事監修:小竿 建(こさお けん)
教習指導員資格者証(普通) 、教習指導員資格者証(普自二) 、運転適性検査・指導者資格者証 を保有。長年にわたり自動車教習所の教習指導員として、多くのドライバーの育成に携わる。警察庁方式運転適性検査の指導者として、運転者の特性に応じた安全運転指導にも従事 。令和元年には、長年の交通法規遵守と安全運転励行、交通事故防止への貢献が認められ、練馬警察署長および練馬交通安全協会会長より感謝状を贈呈される 。豊富な指導経験と高い安全運転意識に基づき、この記事の内容を監修。
🔗 関連リンク
- 【東京でペーパードライバー講習を探すなら】FAQ&体験記
- 【初回お試しコース90分|出張エリア一覧】
- 【板橋区×テスラ】出張講習の体験記
- 【自己診断チェックシート】運転再開の不安を見える化
- 【運転が怖くなった方へ】再出発を支える講習体験談
📣 本記事の企画・取材・構成について
本記事は、東京ドライビングサポートの広報・マーケティングチームによる現場取材と分析をもとに構成されています。
取材・企画・構成を担当したのは、広報ディレクター 板倉 智(いたくら さとし)。
SNS運用やSEO対策にも精通し、「伝わる・検索される・信頼される」広報発信を推進しています。


